北京市海淀区にある「四通橋(しつうきょう)」は、車と歩行者が通行する、ごく普通の陸橋であった。しかし、今やその「四通橋」は、ある特殊な意味をもつ地名となっている。
昨年10月13日の正午ごろ、北京「四通橋」の上に、習近平政権を真っ向から批判するとともに、その最高権力者である現国家主席に対して「独裁の国賊、習近平を罷免せよ!(罢免独裁国贼习近平!)」と名指しで罵倒する横断幕が掲げられた。
これに対して、何よりも自身の面子を重んじる習近平氏が、おそらく卒倒するほど激怒したことは想像に難くない。
しかし、その横断幕に手書きされた文言は、極めて「真っ当な要求」であり、中国で生活する民衆の誰もが共感できる内容であった。今月13日、世界を驚かせたこの「四通橋事件」から1周年を迎えた。
その名は、彭載舟(ほうさいしゅう)氏
「四通橋」に掲げられたスローガンには、「独裁の国賊 習近平を罷免せよ」と書かれていたほかに、まだ当時は「ゼロコロナ(清零)政策」中であったことから「PCR検査は要らぬ、食べ物が欲しい。封鎖は要らぬ、自由が欲しい」の文言があった。
さらに「嘘は要らぬ、尊厳が欲しい。文革は要らぬ、改革が欲しい。独裁者は要らぬ、選挙権が欲しい。奴隷になるのは嫌だ 、公民でありたい」と書かれていた。
なにしろ強権で抑えつけていた民衆から、手痛いカウンターパンチを食らったのである。中国共産党は、表面上はともかく、このような「真っ当な要求」を突きつけられたことに驚嘆し、反抗する民衆を前にして心底震え上がったに違いない。
実際、この「四通橋事件」は、それに続く中国民衆の示威活動である「白紙革命」や「花火革命」の先駆けとなった。中共当局に与えた衝撃の大きさは、この「四通桥(四通橋)」という何の変哲もない地名が、中国のネット上で検索不能になったことからも伺われる。
「四通橋」の上に横断幕を掲げたのは、たった1人の無名の市民であった。多くの中国人はそこに、まるで「三国志」の英雄・趙雲子龍のごとく、単騎で数万の大軍に斬り込んでいく勇者の姿を見た。
その人物。彭載舟(ほうさいしゅう)氏(本名・彭立發)は「四通橋の勇士」と呼ばれ、以来、中国政府に立ち向かう人々の象徴的存在となった。
「ブリッジマン」は生きている
欧米のメディアは「四通橋の勇士」を、89年の六四天安門事件の際に戦車の前に1人で立ちはだかった「タンクマン」の姿を重ねて報道するとともに、この勇士に「ブリッジマン」の尊称を付与した。
その場で取り押さえられた彭氏は、当局に連行されて以来、外界との接触を一切断たれ、その安否もふくめて現在も所在は分からない。彭氏の妻子は郷里で軟禁されている。彭氏の姉まで失踪して、行方不明の状態だという。
米政府系放送局のボイス・オブ・アメリカ(VOA)が情報筋の話として報じたところによると、彭氏が今どこに拘束されているのかは分からないが「(彭氏は)今でも生きている」という。ただしVOAは「彭氏に関する案件が司法手続きに入ったという情報は、今のところない」とも報じている。

米議員「彭氏をノーベル平和賞候補に推薦」
「四通橋事件」から1周年を迎える今月13日、米下院の中国特別委員会で委員長を務める共和党のマイク・ギャラガー議員は「世界は彼(彭載舟)の物語を知る必要がある」として、彭氏をノーベル平和賞候補に推薦した。
米誌「タイム」が4月に発表した、今年の「世界で最も影響力のある100人」のリストのなかにも、彭載舟氏の名前があった。なお、この「100人」のなかで日本から選ばれた人物は、岸田文雄首相とゲーム開発者の宮崎英高氏である。

中共に単独で立ち向かった「勇士」
結論から言えば、今の中国の一般民衆は、中国共産党に対して(その内心においては)全く支持していない。もはや、半世紀前の毛沢東時代ではないのだ。
しかし習近平氏は、経済危機をはじめとする今の中国が抱える多くの難局を、かつての「毛沢東方式」を取り入れることで乗り切ろうとしているらしい。それは、習氏自身が毛沢東のように、中国人民の崇拝の対象になることだ。
もちろん、時代錯誤も甚だしい暴挙である。それによる中共の崩壊は加速される一方だが、その当人である習氏は、いま目もうつろになっているほどだ。
いくら側近を粛清しても、習氏が抱える巨大な不安は消えない。習近平氏にとって不幸なことは、習氏の周囲は自身が選んだイエスマンばかりであるため、政策の誤りを正すよう習氏に諫言できる気骨ある人物が1人もいないことだ。
確かに、子供のころからの洗脳の結果、小粉紅(若い世代の民族主義者)となった人々もいる。しかしそれは、反日や反米の情報ばかりを大量に注入されたことによる、まことに歪んだ愛国の形態でしかない。こうした愛国洗脳は「今の中国が異常であること」を隠蔽し、糊塗するだけのものである。
そのような「小粉紅」とは全く別に、今の中国が多くの不条理を抱えており、そのため「普通の生活さえできない」ということを実感している人は、まさに民衆のなかにいる。いくら中共が人民を洗脳しても、中国人が本当に幸せにはならないことは、民衆の生活感覚として「明白な事実」なのである。
確かに「明白な事実」ではあるが、そうした異議者に対する中国政府の強権的な弾圧は激しい。そのため、ほとんどの民衆は声を上げたくても上げられないのが現状だ。それは勇気の有無だけでなく、命を失う危険性もふくめて、声を上げた個人にふりかかるリスクが大きすぎるからである。
そのようななか、彭載舟氏が出た。日本史でいえば、源平時代の騎馬武者のような大音声(だいおんじょう)を上げた。あるいは、風車に突っ込むドン・キホーテと言ってもよいが、それを嘲笑する民衆はいなかった。皆、彭氏に賛同し、同じことを思っているからだ。
手製の横断幕を陸橋に掲げるという、まことに古典的な方法ではあったが、それがかえって功を奏したのかも知れない。インターネット上で反政府運動を企図すれば、すぐさま中共の検閲に引っかかっただろう。
こうして、中共に単独で立ち向かった「四通橋の勇士」彭載舟氏は、世界にその名が知られる「ブリッジマン」となった。逃げもせず、陸橋から飛び降り自殺もせず、その場で逮捕されることを覚悟の上での行動であった。
「重い沈黙」を突き破った大功績
米国在住の中国人権弁護士・呉紹平氏は、次のように述べた。
「(中国の)社会全体が、重い沈黙に沈むなか、彭載舟氏は街に出て横断幕を掲げ、スローガンを叫んだ。その行為自体が(中共を)非常に震撼させるものだった」
彭氏が「四通橋」に掲げた横断幕には「独裁の国賊、習近平を罷免せよ」と書かれていた。
さらに「PCR検査は要らぬ、食べ物が欲しい。封鎖は要らぬ、自由が欲しい。嘘は要らぬ、尊厳が欲しい。文革は要らぬ、改革が欲しい。独裁者は要らぬ、選挙権が欲しい。奴隷になるのは嫌だ 、公民でありたい」とあった。
その言葉の全てが、市民の誰もが心に思っていながら口に出せない「禁じられた本音」であった。それは同時に、中国共産党が最も恐れる「民衆の覚醒」でもあると言ってよい。
彭氏は橋の上の抗議活動と同時に、中国人民に対して、中国共産党に反抗して立ち上がることを提唱する一連の文章を公表していた。
それについて、呉紹平氏は「彭氏が主張したのはスローガンだけではない。中国社会のあり方をどのように変えるか、そして中国共産党による独裁体制をどのように解体させるのか。さらには、独裁体制下の中国をどのようにして民主や自由、立憲政治に向かわせるのかについても表明した」と述べた。
その上で、呉氏もまた「彭氏がノーベル平和賞にノミネートされるのは当然だ」と評価した。
「白紙革命」の呼び水になった
元弁護士の梁少華氏は、次のように述べた。
「昨年12月まで、3年間に及んだゼロコロナ政策によって、多くの人々は飢え、医療を受けることもできずに命を落とした。彭氏は、ゼロコロナ政策の終了に直接的な影響を与えることになった白紙革命のきっかけを作った。だからこそ彭氏がとった行動の意味は、とてつもなく大きい」
さらに梁少華氏は「怒りの民衆を前にした中共は、ゼロコロナを突然終了した。このことを通じて、中国共産党がいかに無力で、内心では民衆を恐れていることが露呈された。彭氏の行動は、それを皆に知らしめたのだ」と話した。
「四通橋の勇士」彭載舟氏は、その陸橋の上で逮捕され、以来消息不明になった。しかし、その悲壮感あふれるワンマンショーはネットで拡散され、人々の記憶に確実に残った。
その不屈の精神に、多くの人が共感した。世界中の人々は、あらゆる場所に彭氏のスローガンと同じ言葉を書くなどして連帯を示すとともに、複数の国際組織や人権団体も彭氏の釈放を中国政府に呼び掛けている。
今年10月13日、あの「四通橋事件」から1周年を迎えるにあたり、世界中で彭氏とその家族の釈放を中国政府に求める抗議デモや支援集会が開かれた。
彭氏が1年前に北京の陸橋にかかげたスローガンが、世界中の支援集会で掲げられた。人々は今、さまざまな形式で彭氏の勇気に連帯の意を示している。


「革命の恐怖」に慄く中共当局
彭載舟氏が反抗開始の狼煙(のろし)を上げた北京市海淀区にある「四通橋」は、中国当局が検閲する言葉のブラックリスト入りした。
そればかりか、ただの道路標識である「四通橋」のプレートまで現場から撤去された。今では「中国産の地図アプリに、四通橋の地名すら表示されない」という指摘もあるほどだ。
事件から1周年を迎えるにあたって、現地の警察は「第二の四通橋の勇士」の出現を阻止するため、北京の「四通橋」で厳戒態勢を敷いていた。
現場付近では、大量の私服警官が通行人を止めて「ここへ何しに来た?」と尋問し、携帯電話の内容をチェックするなど検問を行っている。現地市民によると、橋の写真撮影まで禁じられているという。
北京に限らず、深センの陸橋でも見張りの警官がいるという。もはや中国当局は、ほとんど「病的な恐怖感」を抱いているようだ。
それはまさに「革命の恐怖」に慄く(おののく)中国共産党の醜態といってよい。中共がいかにあがいても、その終焉の時は確実に近づいている。





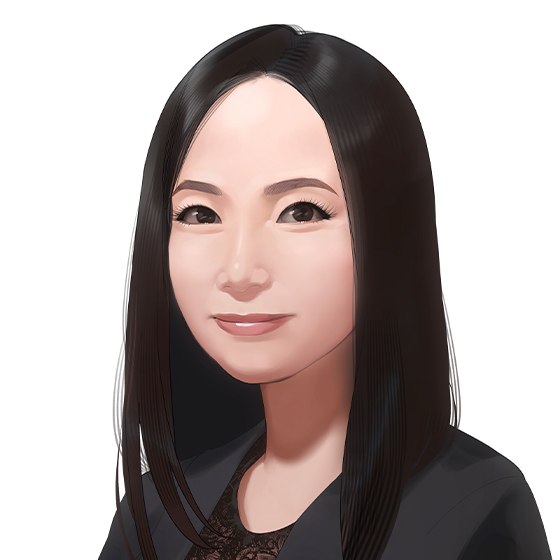







 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。