新型コロナウイルスに対する新たなワクチンとして導入された「レプリコンワクチン」について、国会でその安全性と政府の対応を問う声が高まっている。5月12日の参議院決算委員会では、川田龍平議員(立憲民主党)が、明治製菓ファルマ社のレプリコンワクチンをめぐり、副反応の報告率の高さや死亡事例の報告数、そして厚生労働省のリスク評価の姿勢に対して疑念を呈した。
レプリコンワクチンは、細胞内にmRNAが送られ自己増幅するという画期的な技術を使用した新型のRNAワクチンであり、従来のmRNAワクチンよりも少量で効果が期待できるとされる。日本では2024年10月から明治製菓ファルマの製品が接種に用いられてきた。
しかし、厚労省が4月に提出した資料によれば、同ワクチン接種後の死亡報告は2件、副反応の報告率は0.0451%だった。これは他社製ワクチンの最高報告率0.0033%と比べて10倍以上の水準にあたる。川田議員は「(レプリコンワクチン)が比較的副反応が少ないと説明されてきたが、実際にはそうなっていない」と述べ、使用の停止を求めた。
これに対し、厚労省の鷲見学・感染症対策部長は、「全件を専門家が評価し、安全性に重大な懸念は認められないと判断している」と答弁。ワクチン接種後の副反応報告は、PMDA(医薬品医療機器総合機構)が集計・分析し、審議会で慎重に評価していると強調した。
しかし、川田議員は、こうした評価をくだす審議会に参加する専門家の多くがワクチンメーカーから研究資金を得ていることにより、利益相反の可能性があると問題視した。
BMJ(British Medical Journal)が2022年6月29日に発表した記事「Covid-19: Japanese medical experts express concern over lack of transparency in vaccine approval process」(BMJ 2022;377:o1538)では、日本の新型コロナウイルスワクチンの審議プロセスにおける透明性の欠如と、専門家の利益相反(COI)に関する懸念が報じられている。
審議会の評価については、新型コロナワクチンにおいて、医師などから2263名の死亡報告があげられているにもかかわらず、ワクチン接種後の死亡とワクチン接種の因果関係が否定できないケースが2名にとどまり、2250名、つまり99.4%が評価不能となっており、疑念を抱いている医療関係者も少なくない。
川田議員は「重大な事象が生じていても、それを重大と評価する専門家の声が議論に反映されない構造になっている」と批判した。
さらに川田氏は、4月2日に共同通信が副反応・死亡の累積件数を初めて報じ、9日にはNHKも報道したことを取り上げ、「ようやくマスコミが累積の数を取り上げるようになったが、これだけの事例が報告されている中で、mRNAワクチンをいつまで使い続けるのか」と政府の姿勢を問い質した。
予防接種健康被害救済制度では、令和5年度までに13577件の申請があり、9135件が認定された。そのうち1006件が死亡に関する認定事例である(厚生労働省・5月12日時点答弁より)。
川田議員は、ICH(医薬品規制調和国際会議)ガイドラインE2Eが示す通り、自発報告から得られる「安全性のシグナル」は政策決定に反映すべきであり、それを怠ってきた政府の姿勢は「政策的過失」と言わざるを得ないと主張した。
副反応報告の累積傾向や、リアルワールドデータ(市販後の実使用情報)を活用したリスク評価がなされてこなかった点も強く批判した。
1960年代に発生した薬害サリドマイド事件も、早期に多数の有害事象報告があったにもかかわらず、それが政策に反映されることはなく、結果として多くの胎児に先天性障害が発生した。川田議員自身も、薬害エイズ事件で、薬害の犠牲になっている。
川田議員は、mRNAワクチンのケースでも同様に「安全性のシグナル」を軽視したまま接種が継続されたことを問題視し、政府の対応の検証を求めた。
これに対し、厚労省・城医薬局長は、死亡症例など特定の事象については専門家による一例ずつの因果関係評価を実施しており、各専門分野から複数の医師が選ばれて評価していると回答。また、その評価結果は審議会で審議されていると説明した。
川田氏は、「これまでのワクチン接種において、重大な事象がないと繰り返すだけの議論では被害の実態が見えてこない」とし、政府が臨床試験や副反応の報告結果についてどのように検証してきたのか、明確な説明を求めた。厚労省職員は、副反応報告はPMDAにより集計され、データベースに整理されたうえで審議会で評価されていると説明したが、報告の内容や評価の透明性についての疑念は残されたままである。









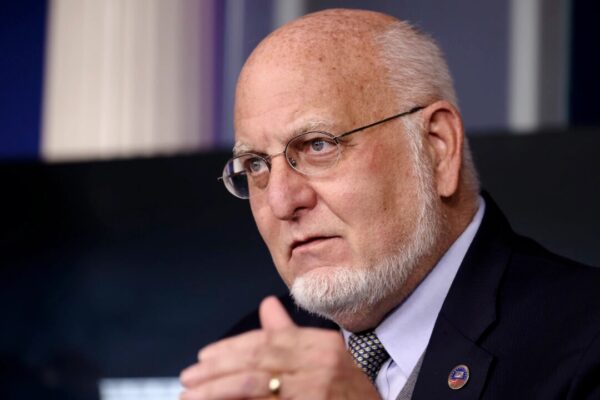

 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。