1999年10月、フランスの日刊紙大手フィガロ(Le Figaro)の編集委員会主席編集委員アラン・ペールフィット(Alain Peyrefitte)は、間もなくフランスを訪問する予定の中国の国家元首江沢民に対して、書面でのインタビューを行い、中国、フランスと世界情勢についての考えを求めた。江沢民はここぞとばかりに、先制攻撃の手法で国際的なメディアを占領し、「邪教」の二文字で、半年前から行ってきた法輪功(ファルンゴン)への暴力的弾圧行為を釈明した。
中共当局がフランスを選んだのには二つの目的があった。一つは、フランスでは以前から、特に世界を驚かせた「人民寺院」(The Peoples Temple)事件以来、行政と司法の双方による一連の措置の実施を通して、各種の邪教がフランスで氾濫するのを防ごうとしてきた。そのため、中共当局は、フランスのこのような特殊な社会事情を利用して、白黒を逆転させ、是非を混同させる絶好のチャンスだと考えたからである。
今一つは、フランスの各大手メディアは市場を争うために、フランスを訪問する外国指導者への単独インタビューをぜひとも行いたいと考えていたからである。中共当局は、フィガロ紙のこの思惑に付け込み、インタビュー内容を全文発表するよう求めた。フランスの政界とメディア界で出しゃばり尽くしていたペールフィットは、もちろん、中共の条件に唯々諾々と従った。
江沢民の訪仏当日、フィガロ紙は約束通り、単独インタビューの全文を発表した。このインタビューの内容はフランス社会に大きな衝撃を与えた。しばらくの間、記者たちは自分では考えもせず人の話を受け売りする者もいれば、口をつぐんで押し黙る記者も現れ、中国大陸で行われている法輪功学習者に対する連行、監禁、拷問、洗脳などについて追及しようとしなくなった。
20世紀の90年代初め、共産主義が中国大陸で40数年にわたって統治を行う中で、数千万の罪のない国民がその害を受け命を落としたことから、国民は共産主義的イデオロギーを大いに疑問視した。こうした中で、「真・善・忍」という価値基準を提唱し、健康保持を目的とする修煉方法―法輪功が現れ、中国の伝統的な気功文化のバックグラウンドの下で、予想外ながらも情理にかなった発展を見せ、中国社会の各階層の民衆に歓迎され受け入れられた。このような「百利あって一害なし」の修煉方法を、当時の官製メディアも称賛し推奨した。しかし、億万の人々が参加するこの煉功活動は、その後すぐに、中共当局から全く違った目で見られることになった。
中共が政権を執って以来、終始変わらず守ってきた原則は、いかなる組織も共産党と並存することを認めないということである。中央から地方までのすべてが共産党自らによる縦割り方式で管理された社会において、これは政権を維持する根本の一つと考えられている。
「人民政治協商会議」に彩を添えているいわゆる民主党派が、それぞれの党の規約の中で、共産党の指導を擁護すると明記しているのが、その明らかな証しであろう。「人民代表大会」や工青婦(労働組合、中国共産主義青年団、中華全国婦女連合会の略称)といった民衆団体をはじめ、工場、学校、商店、町内会、農村に至るまで、均しく党グループあるいは党支部を設立することこそ、中国大陸特有の政治的現実である。ところが今日、法輪功が出現し、それが提唱する価値観は、共産主義が提唱するものと正反対であるにもかかわらず、共産党員を含む億万の民衆に敬愛されている。当時の東欧とソ連の解体に鑑み、中共当局は疑心暗鬼になり、非常に恐れ、法輪功は正にポーランドの独立自主管理労働組合のような存在だと決めつけた。
この結論が出されると、法輪功に対する狂気じみた野蛮な弾圧が始まり、1989年の天安門事件以来、またもや多くの罪のない中国人が共産主義の犠牲者となったのである。これまでの幾多の政治運動と同様に、嘘とでたらめで塗り固めた一大批判キャンペーンを皮切りに、全国規模の捜査逮捕、監禁、拘留、洗脳などの手段が採られた。その目的は、でたらめな罪名を付けて、真相を知らない一般民衆を脅迫し、当局と一緒になって各方面から法輪功を「消滅」させようとすることであった。
1956年、私の大学生活が始まった。私は他の多くのクラスメートと同じく、バスケットボールが好きで、クラスでバスケの試合をやろうとみんなで決めた。第一試合が始まる直前、私たちより年上のあるクラスメートが突然試合会場に現れ、私に向って、顔をこわばらせ厳しい表情で、「何をするつもりだ」と言った。私は「バスケの試合をやるんだ」と答えた。
「バスケの試合?党支部に報告しているのか?」と問い詰められ、「こんな程度のこと…、報告していない」と答えた途端、叱責するような口調で、「党支部に報告していないなら、解散だ」と命令した。彼は入学前から共産党の幹部で、1年生の党支部書記だということを、クラスのみんなは初めて知った。私もこれで共産党の組織的原則の手ごわさを初めて知ることになった。
翌年の1957年、「反右派」運動が始まる前触れとして、共産党の機関紙である人民日報が「これはなぜか」と題する社説の発表を皮切りに、長ったらしい大量の批判文章を掲載し、次々にいわゆる「反党反社会主義右派分子」の物語が捏造された。20数年後、当時「右派分子」にされたクラスメートと再会した時、みんなは互いに困惑した様子で顔を見合わせた。私のほうから「もう右派分子でなくなったのか」と聞くと、彼は「彼らは、私に張り付けたレッテルを自らはがした」と苦笑いしながら答えた。
1966年から始まったいわゆる「文化大革命」も、ある歴史劇への批判からスタートした。紅衛兵が新華社総編集室を占領した後のある日、私は偶然、当時すでに「牛鬼蛇神」(文化大革命中に階級の敵とされ批判の対象となった各種の人々)とみなされ、社内で労働改造を強いられていた穆青社長と会った。私は怪訝そうに「あなたはなぜ資本主義の道を歩む実権派となったのか」と聞いてみたところ、穆青社長は、「私?…30年間革命してきたのにマルクス・レーニンに通じない」とぼうっとした様子で答えた。
1989年6月3日の夜、私はパリから直接北京へ電話をかけた。一体何があったのか、誰が「広場の暴徒」だったのかと詰問したところ、電話を取った人は、ただ一言、「何も聞くな、本社はすでに軍の管制下に入っている」と言って電話を切った。大きな運動のたびに、まずマスコミ部門をコントロールするのが、独裁政権のいつもの手法である。
マスコミによる法輪功批判の攻勢は、1996年6月17日付の光明日報の記事を皮切りに始まり、10数社の新聞、雑誌が命令によって同調した。1999年7月23日、中共の機関紙・人民日報が「認識を高め、害毒を見極め、政策を把握し、安定を維持する」と題する社説を発表し、法輪功を「非合法組織」と厳しく批判した。これをきっかけに、法輪功を取り締まる弾圧のラッパが吹き鳴らされた。同時に、当局は自らのコントロール下に置く宗教界、民間団体、学術団体を動員して、談話を発表したり座談会を開催したりして、ありもしない罪名によって、容赦なく法輪功に批判を加え、空前の惨烈な政治運動がまたもや展開された。
中共当局が法輪功に貼るレッテルの名称は、ころころ変わった。「非合法組織」、「邪教組織」、「反動敵対組織」、「西側反華勢力の政治的道具」、「反政府組織」、「反動政治組織と政治勢力」、「テロ組織」などである。これらの出任せのレッテルに、フランスの同業者たちもしきりに疑問を抱いた。
私は1989年の北京六四事件をきっかけに新華社を辞めた。その後フランス国際ラジオ放送の理事会の要請を受けて、フランス国際ラジオ放送中国向け中国語放送部の創設に加わった。冒頭で述べた江沢民のフランス訪問後間もなく、駐仏中国大使館から、中国向けラジオ放送について、フランス国際ラジオ放送の理事長との会談を求めてきた。理事長のジャン・ポール・クルーセル(Jean-Paul Cluzel)は、フランス国際ラジオ放送の中国語部の主任も同席させたいと提案したが、中国大使館に執拗に拒否された。会談後、クルーセルは私に「紅衛兵と会ってきた」と笑いながら皮肉った。
その後、別の大使館員が私との面会を求めてきた。彼は冒頭、次のように面会の主旨を話した。「今あなたに話したいのは、法輪功のことだ。あなたが統括している中国語ラジオ番組の中で今後は法輪功のことを放送しないように」とのことだった。なぜかと聞くと、彼はすぐさまこう答えた。「法輪功は邪教だ。ここに多くの資料を持ってきた」。そう言って、机の下から大きな袋を取り出した。中には法輪功を侮蔑する宣伝資料、小冊子、宣伝用ポスター、ビデオ、CDなどがいろいろと入っていた。
私は彼に明確に伝えた。「邪教というのはあなたたちの考えだ。フランス国際ラジオ放送は誰の指図も受けない独立したメディアだから、法輪功問題に関して独立メディアによる調査が未だないにしても、我々は報道しないわけにはいかないし、あなたたちの意向に従って法輪功のことを放送するわけにもいかない」。さらに、法輪功がすでにあなたたちによって政治的そして国際的な問題にされた以上、大陸当局はすべてをオープンにして、国際的なメディアによる法輪功問題への独立調査を許可すべきだと提案した。
江沢民のフランス訪問後しばらくして、駐仏中国大使館のホームページに、法輪功について宣伝教育する専門コーナーが設けられた。このような、一国の外交分野にまで及ぶ容赦なき狂気は、一時的に人々を騙すことができたかもしれないが、同時に、この種の宣伝に対する人々の警戒心や疑念を呼び起こしたのも事実である。
江沢民がフィガロ紙を利用して、フランスの世論とフランス国民を騙す手口は、フランス当局と有識者による法輪功の真相を探求する努力を阻むことはできなかった。フランス政府は、2002年11月、首相官邸直属の「邪教の氾濫に対する警戒と取締り」を目的とする省庁間専門チームを立ち上げた。その任務は、「基本的人権や自由に対する侵害及びその他の非難すべき反社会的行為を摘発し、邪教現象に対する取調べや分析を行う」ことである。「公権力との協調を図り、各種邪教の氾濫に対する警戒と取締りの実施」も担当する部署である。
しかし、これまでフランス政府は法輪功を、警戒し取り締まるべき邪教団体として認定したことがない。毎週週末になると、法輪功学習者はエッフェル塔の前とほかに2か所の公園で煉功活動を続けている。法輪功学習者からなる天国楽団は、フランス当局主催の大型文化イベントにも出場している。彼らはフランス国民議事堂内で、法輪功に関する真相報告会や討論会を幾度も行ってきた。
おもしろいことに、フランス警察当局は、法輪功学習者からの駐仏中国大使館前での平和抗議活動の申請に対して、長年、口実を設けて許可して来なかった。2009年7月、法輪功学習者は本件に関して、フランスの司法当局に対してフランス警察当局(la prefecture de police)を相手に提訴を行った。パリ行政裁判所(letribunal administratif de Paris)は、最終的に、緊急訴訟裁判官の裁定(l’ordonnance du juge des referes)により、法輪功側勝訴の判決を下した。フランス警察当局は敗訴し、フランスの法輪功協会に対し1,000ユーロの賠償金を支払うよう命じた。
外国人にとって、中国の伝統文化や共産中国に対する十分な理解がなければ、法輪功の真相について理解するのは確かに難しいことかもしれない。中国において、様々な時期の共産主義被害者のうち、法輪功修煉者は、抑えつけることも消滅させることもできない稀有の団体である。法輪功は率先して、暴政に反抗する檄文「共産党についての九つの論評」を発表し、全面的に共産党の本質を明らかにした団体である。法輪功はまた、中国マスコミ史上の先駆けとなり、弾圧を受けてどん底にある時に立ち上がり、海外で大紀元時報、希望の声ラジオ放送、新唐人テレビなど一連の独立メディアを創立した団体である。法輪功は、国際組織や諸外国の裁判所に中国の指導者を相手に告訴を行っており、これも前代未聞のことである。また、近年、中国の伝統文化の復興を目指す「神韻芸術団」による世界公演ツアーや各種国際文化コンテストなども世界で脚光を浴びている。法輪功修煉者はその他の共産主義の被害者とともに、中華民族が最終的に共産主義によって強いられた苦難から離脱し、民主自由の歴史的潮流に融け込むために弛まぬ奮闘を続けている。
暴政に対抗するこれまでに見られない団体、歴史的舞台に押し上げられたこの団体の修煉者たちは、自らの心を鏡の如く澄み渡らせ、世相の塵埃を拭き取ることさえできれば、きっとこの世界における善良な夢を叶えることができるであろう。「蒼生帰正道 江山復清明(蒼生は正しい道へ戻り 江山は再び明るく清らかになる)」。私は固くそう信じている。
法輪功が迫害を受け始めて間もなく、「訪民」と呼ばれる人々が北京でよく見られるようになった。一党独裁の下における表面的な経済繁栄に覆い隠され、悪徳汚職役人に威圧されて一家離散し、冤罪を訴え申し立てる所のない民衆たちは、近年、危険を冒しながらも北京へ集まり、少しばかりの正義を求めようとしている。結局は、往々にして門前払いされ、投獄されることもある。我々は、彼らは中国最後の共産主義被害者になることができるのか心配している。当局が彼らに押し付けるレッテルは、いまだ定説がないようだ。
共産主義の罪悪を無視し、人を冷酷無情に見殺しにし、超国家主義のために弁明し、時にはちっぽけな利益を得ようと働いている「瀟洒君子」たちは、その一時の驕りによって、彼らや彼らの子孫までもが千古の悪名を背負わなければならなくなることに、思いを馳せたことがあるであろうか。
本文冒頭で言及したあのフランスの名士、アラン・ペールフィットは、「周恩来の魅力に陥って抜け出せない」人だと言われている。彼が死んだ後、中共当局は武漢大学のキャンパス内に、学生たちが仰ぎ見るための銅像を建てた。彼について、中国の若者は何を思い出すことができるだろうか。中共の党首江沢民の手下となり、残酷な迫害を受けている中国人団体に対する事実無根の誹謗中傷をしてきたほかに、1973年、「中国通」と呼ばれた彼は、『眠れる獅子が目覚めた時、世界は震える』と題する本を出版し、狂気たる文化大革命の時代の中国大陸のお先棒を担ぎ尽くしていたことが挙げられよう。彼の身辺の人が後になって、この本の中で見える中国は、「まさに周恩来が言っていた中国そのものだ」と語った。作者によれば、多くの人口を抱え、充実した経済技術力さえあれば、中国は世界に立ち並ぶことができるという。中国人はよく「三足鼎立」という言い方をする。ペールフィットの著書の読者は次のように指摘する。「民主主義の理念がなく、共産独裁体制も放棄しなければ、中国の勃興はただ絵に描いた餅にすぎない」。
執筆者紹介
呉葆璋(ご ほしょう):報道専門家、元新華社国際部記者、フランス国際放送局の中国語部門初代主任。


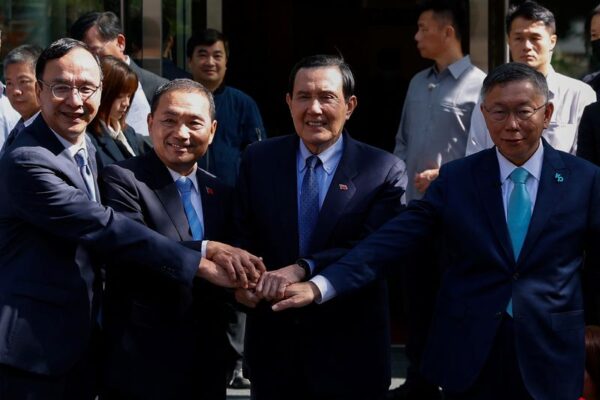

 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。