北京在住の弁護士・余文生氏は、2014年9月に香港で起きた民主化要求運動、いわゆる「雨傘運動」を支持した人権活動家である張宗鋼氏の弁護を引き受けたことで、同年10月に突然、中国当局により拘束された。
死と隣り合わせ 獄中で凄惨な拷問
余氏は北京市内の大興区看守所に連行されると、「大環背銬」と呼ばれる凄惨な拷問を受けた。 余氏の身体に強烈な負荷がかかり、両手は見る間に腫れ上がった。その上警察は、さらなる苦痛を与えるために手錠の部分を引っ張り続けた。余氏は叫び声をあげた。
のちに余弁護士は、その耐えがたい苦痛を「死んだほうがまし」と表現しているが、この時「死は自分のすぐそばにあり、命とはこんなにもはかないものだったのか」ということを初めて実感したという。
11月2日夜から11月5日早朝にかけて、余氏に3回の「大環背銬」が行われた。腹膜が内部で裂け、内側から小腸が飛び出してしまった。だが、拷問による苦痛があまりにも大きかったため、10日も経ってから、痛みにより鼠形ヘルニア(脱腸)を発症していることに気が付いたという。鼠形ヘルニアとは、腸(や腹膜)の一部が本来の位置から動いて筋膜の間から皮膚の下に出てくる症状。
11月20日、余氏は北京市第一看守所に移送されたが、この時の身体検査で鼠形ヘルニア症状が確認されている。だが警察はそれを認めなかったばかりか、何の治療も施さず、「家系の遺伝的な問題」と言った。
拷問の目的は、人を服従させることだ。だが中国当局は、この拷問と牢獄体験が、余文生弁護士の人生を大きく転換させることになるとは思いもしなかっただろう。
学区での生活、民主主義を学んだ少年時代
1967年、余氏は北京鉱業大学の敷地内の街で生まれた。北京の政府機関職員の住む集合住宅で育ち、生活水準は高く、一部の政府高官と顔を合わせることも多かった。
余氏の父親は空軍の技術士官だったが、退役後は旅行局に就職し、外国の賓客を接待する業務で責任者を務めていた。当時、こうした業務は実質的に政府機関の仕事に属しており、余氏の父親もある種の特権的な立場にあった。
仕事で多忙だった父親は、「明報」や「大公報」といった香港の新聞や、党幹部しか見ることのできない「内参(内部参考資料)」を家に持ち帰ってきたこともあった。当時のような閉鎖的な時代において、こうした情報が一般人の目に触れることはなかった。
余氏は少年時代から、こっそりと内部文章や香港の新聞を読みふけっていたと語っている。そのため、西側の民主主義や普遍的価値観も自然に受け入れることができた。その結果、父親に「華国鋒は失脚する」「ソ連は解体される」「中韓の国交正常化が実現する」といった予測を語るほどになっていた。
余氏の考え方は同世代のそれとはかなり異なっており、高校時代には既に、「中国共産党政権は独裁政権だ」との持論を持っていた。
そして「民主主義社会への転換は時代の趨勢であり、中国も将来は必然的に民主、法治国家への道を歩むことになるだろう」といった考えもまた、余氏が弁護士という職業を選択する理由の一つになっていた。
35歳の2002年から、弁護士として正式に活動を始めたが、このころは主に商業関係の民事訴訟を専門に取り扱っていた。余氏は獄中体験について「もし当局に拘束されていなかったら、今でもこうした商業関係の訴訟しか引き受けていなかったと思う」と当時を振り返っている。
死刑囚専用の監房へ
14年、最初に収監された北京大興看守所で38日間拘留された後、同氏はその身柄を北京市第一看守所の死刑囚専用の監房に移された。ここでは61日間にわたり拘留されている。
死刑囚の監房には12人が収容されており、そのうち4人が死刑囚、6人が死刑囚の面倒を見ながら監視する囚人「陪号」で、余氏もまた「陪号」を命じられていた。
監房内の一切を取り仕切る部屋頭を務める囚人は、余氏に対し、「ここにきた政治犯のうち9割以上が我々に服従した。服従しない者は更なる手段が待ち構えている。自分はここに8年過ごしているが、根をあげなかった政治犯は見たことがない」と言ったという。
死刑囚の監房では、精神的な重圧が降りかかった。死を目前に控えた死刑囚はどんな行動に出るか分からない上、ここいる間に余氏は、約100回の尋問を受けた。尋問のたびに、余氏は妥協を選ぶか、それとも人間の尊厳を保ち続けるかで必死にもがき、そして次のような結論に達した。
「君が一歩退けば、彼らは一歩詰め寄ってくる。君の退路が絶たれるまで、彼らの対応はますます厳しさを増してゆくのだ。人としての尊厳のかけらもないところまで追い詰める。彼らのやることに最低ラインはないのだから、死に至るまで君をいたぶり続ける」。
(つづく)
(翻訳編集・島津彰浩)



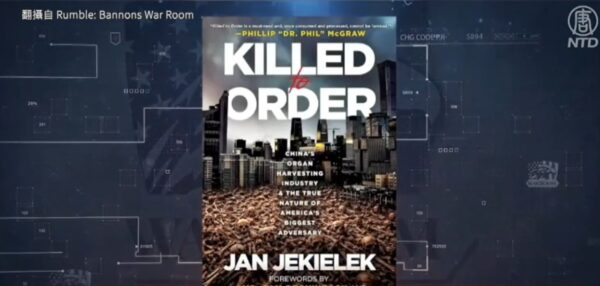





 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram



ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。