春秋時代、千古の名相と称される管仲という人物がいた。彼は斉国の桓公を補佐し、春秋時代の覇業を成し遂げ、民を豊かにし国を強くした。孔子でさえも「管仲が桓公を補佐し、諸侯を制し天下を安定させたことで、民は今なおその恩恵を受けている」と感嘆している(論語・憲問)。
つまり、斉国の宰相である管仲は桓公を助けて諸侯を統一し、天下を安定させた。その恩恵は後世の民にも及んでいるということだ。
彼の方法は戦争や重税に頼るものではなく、民を安定させ豊かにすることを基盤とし、それによって国家を富強にした。そして税収は自然に充実していった。さらに、災害や困難な年には減税や免税を行った。
諸葛亮も管仲を称賛して「忠実で知恵深く、民を救済した」と述べている(管子注)。管仲は民の救済を本心とする智慧ある忠臣だった。
管仲は古代において最も経済と財政に精通した政治家である。彼が残した著作『管子』には、災害時の免税、塩鉄の官営化、商品価格への課税など、実用的かつ先進的な治国策が提案されている。これらの思想は現代でも人々を驚嘆させるものだ。
では、具体的に彼はどのように行動したのか? その智慧は現代人に何を教えてくれるのか? 以下では三つの実例と諸葛亮による応用から説明する。
一:災害の年は税を免除し、国と民を救う
『管子・小匡』には次のような記述がある。斉国である年、大きな水害が発生した。桓公は国の税収が大幅に減少するのではないかと心配し、管仲にどうすればよいか尋ねた。
管仲はこう答えた。「災害の年ならば税を軽減し賦役を薄く。年が豊かならば余剰を倉庫に蓄え、水害や干害へ備える。農時を奪うことなく、民力を過度に搾取することもしてはならない」つまり、災害が起きた年は税を減らし、民衆が立ち直れるよう助けるべきだということだ。一方で、豊作の年には余剰分を蓄えておけば、いざという時に国も困らない。
要するに、国君は自分の国庫が空になることだけを心配していてはならず、民衆への配慮と支援を忘れてはならない。民衆が災害に遭った直後に税を強制的に徴収すれば、それは苦境に追い打ちをかけることになり、生計が立たなくなった民衆から税など到底徴収できるものではない。しかし、もし税を免除し、まず民衆が生活を立て直せるよう助ければ、翌年の豊作時には自然と感謝の念から進んで税を納めるようになるだろう。
桓公は管仲の提案を受け入れ、その年は税を徴収しないことを決定した。翌年には天候が安定し、民衆は喜んで自発的に穀物や税を献上した結果、国庫は前年よりもさらに充実した。
俗語で言えば、これこそ真の「賢い財務管理」であり、「優れた理財術」だと言える。
諸葛亮の政治手腕を見る(1)
蜀漢建国初期、国家の力は弱く、民衆は困窮していた。諸葛亮が政務を執る際、重税を急いで課すことはせず、「薄賦簡徭」(軽い税と簡素な労役)という政策を実施した。
特に南征で孟獲を平定した後、彼は「秋後算賬」(戦後に厳しい追及を行うこと)をせず、南中で大赦を行い税を軽減し、民衆を慰撫した。
『三国志』などの歴史記録によれば、「百姓皆安堵如故,願為上用」(民衆は皆安心して平穏に暮らし、国家のために尽くすことを願った)とある。その結果、南中は数十年にわたり安定し、戦乱もなくなり、むしろ国家としての基盤が強固になった。
両宰相(諸葛亮と管仲)は共に、「一時の寛容が百年の安定をもたらす」という道理を理解していた。
二:塩鉄の官営化と「税を価格に隠す」政策
『管子・軽重』には、管仲が非常に進んだ政策を提案している。
「国家は塩や鉄といった生活必需品を掌握し、その価格を設定することで税を『価格に隠す』ことができる。民衆が買う際には多少高い金額を支払うことになるが、自分たちが直接税を取られているとは感じないだろう」と述べている。
これが後世で言う「寓税於価(ぐうぜいおか)」(税を価格に含める)という方法である。この方式は、国家の収入を確保しつつ商人が価格を吊り上げるのを防ぎ、さらに民衆から不満が出ないようにするという利点があった。
諸葛亮の政治手腕を見る(2)
蜀の地は塩や鉄が豊富に産出されるが、輸送が困難であった。諸葛亮は管仲の方法を模倣し、国家が核心的な物資を管理し、市場価格を用いて財政収入を調整する仕組みを設けた。これにより、追加の税を徴収する必要がなくなった。
彼は「塩井」「鉄官」という管理機関を設置し、収入を確保するだけでなく、塩や鉄を用いて食糧や布と交換し、戦争の支援や民衆の生活を支えた。この政策には民衆への思いやりが自然に表れている。
諸葛亮は人々に税を強制するよりも、資源を巧みに活用する方が良いことを理解していた。国家と民衆が互いに利益を得る仕組みを構築し、権力で人々を抑圧して搾取することは避けたのである。
三:国富は民の財を奪うにあらず、民の力を養うことにあり
管仲は「国は民を本とし、民は食を天とする」という治国の思想を提唱した。
彼は国家が干渉を減らし、自由に百姓が農業や商業に従事できるようにした。国家は園丁が花を育てるように、民が自ら富むようにするべきだと考えた。結果として数年後、斉国の百姓は「家々に余糧があり、各戸に蓄えがある」状態となり、商人が集まり、穀物の価格も安定し、斉国は春秋時代の第一の強国へと躍進した。
諸葛亮の政治手腕を見る(3)
蜀漢では「人少なく地多し」という状況であった。諸葛亮は搾取によらず、「屯田制」を実施した。この制度は流民を安置し耕地を増やすものであり、百姓が耕作して得た糧食を国家も軍糧として蓄えることができた。
後世の人々は彼を称えてこう述べた。「官吏と民は安定して業務に励み、人口は増加し、倉庫には穀物が満ちている」
民が富めば、国も強くなる。
つまり、真の国富とは民をまず富ませることである。
今日、私たちは何を学んだのだろうか?
現在、多くの国や都市が経済不況に直面すると、非常に非合理的な方法、すなわち増税を選択している。例えば、消費税の引き上げなどが挙げられるが、その結果として人々はお金を使うことを恐れ、経済はさらに冷え込む。
しかし、古代の賢人である管仲はすでにこう警告している。
「賦斂(ふれん)時ならざれば、民その生を安んぜず」(管子)
これは、時機を考えずに税を徴収すれば、民衆は生活できなくなるという意味である。
また、諸葛亮も「民惟(これ)邦(くに)の本、本固ければ邦寧(やす)し」(尚書)という古訓を守り、民衆こそ国家の基盤であり、その基盤が安定してこそ国家も平穏であると考えた。
経済が冷え込んでいる時に必要なのは増税ではなく、むしろ減税や税負担の緩和、生計支援や活力の養成である。民衆が豊かに暮らせるようになれば、経済は自然と回復し、それによって国家も収入を得ることができる。
結論 税収管理は治国の姿勢である
管仲が主張したのは「税を取るな」ということではない。むしろ、税収とは治国の姿勢そのものであり、時勢に応じて民衆を思いやる知恵であると理解していた。
古人曰く、「富を民に蔵す、国の大計なり」。
今日の為政者には、「羽毛をむしって暖を取る」ような短期的利益追求ではなく、「根を養い木を護る」ような長期的視点を持つことを願いたい。
民が安らかであれば国家は富む。この教えは決して机上の空論ではなく、千古の名宰相たちによって証明された智慧なのである。










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




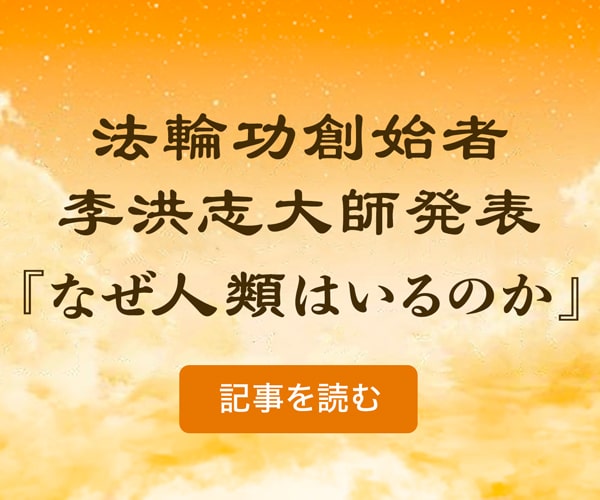
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。