最近、日本の児童・生徒の自殺率が上昇しているという痛ましいニュースが広く注目を集めている。成人の自殺者数が減少傾向にある一方で、子どもたちが新たな犠牲者となっている。社会は進歩し、技術は発展し、物質的な不足は解消された。それにもかかわらず、なぜ子どもたちの心はますます孤独と苦しみに苛まれているのだろうか。
この問題に直面したとき、私たちは問わざるを得ない、「何が間違っているのか?」 。豊かな社会において、なぜこれらの子どもたちは生きる理由を見いだせないのか?
これは教育の迷失と言えるかもしれない。私たちは進学率、競争力、才能、効率性を追求するあまり、教育の本質を忘れてしまったのではないだろうか。
実は、二千年以上も前に孔子がこの問いに対する答えを示していた。
すべての人に教え、愛をもって導く
孔子は「有教無類(すべての人に教えを施す)」という言葉を残している。貧しい人でも、身分が低い人でも、学びたいという意志さえあれば、孔子は喜んで教えを授けた。彼はどんな学生にも耳を傾け、心を込めて導いた。また、「仁者、愛人(仁とは人を愛すること)」と説き、教育の本質は人を支配したり形作ったりすることではなく、愛と理解によって人々の心を善へと導くことだと強調した。
ある時、孔子は弟子の子路に「村の人たちを助けたことがあるか?」と尋ねた。子路が「いいえ、彼らは私の親戚ではありません」と答えると、孔子は嘆いてこう言った。「それでは本当の孝(親孝行)とは言えない。真の孝とは家族への愛から始まり、それを広げて周囲の人々にも及ぼし、自分と同じように他人を愛することだ」。
これは現代の教育に欠けているものではないだろうか。我々は子どもたちにテストで良い点を取る方法や競争で勝つ術を教えているが、「他人を思いやり、自分と同じように愛する心」を教えることができていない。
孔子は生涯で三千人もの弟子を育て、そのうち七十二人が賢者として名を残した。彼は学生を選ぶ際に地位や出身、貧富で差別することなく、「有教無類」の理念を実践した。
特に貧しい弟子だった顔回という人物について、孔子は深く感銘を受けていた。顔回は粗末な小屋に住み、質素な食事しか取れない生活だったが、それでも楽しみや喜びを失わず穏やかに過ごしていた。その姿に孔子は「顔回は本当に賢い。粗末な食事と飲み物で貧しい暮らしにも耐えながら、その楽しさを変えないとは素晴らしい」と感嘆したのである。
これは、いわゆる成功哲学を教える話ではなく、「どう生きるべきか」を考える生命の教育である。孔子が大切にしたのは、人の内面にある揺るぎない意志や品性を磨くこと。外見的な条件や成果には重きを置かなかった。
あるとき、弟子の子貢が孔子に尋ねた。「先生、貧しいことと裕福であることでは、どちらを目指すべきでしょうか?」。孔子はこう答えた。「貧しくても心穏やかで幸せに過ごせるなら、それは素晴らしいことだ。しかし、裕福でありながらも礼儀正しく、謙虚で人を思いやれるなら、それはもっと素晴らしい」。
この話が伝えているのは、「どんな状況でも、品格と礼儀を持つ人であることが、本当の豊かさであり、人生の価値だ」ということだ。
また別の機会に、孔子が弟子たちに「君たちの夢や志は何か」と尋ねたとき、多くの弟子は「立派な官職について世の中を救いたい」「大きな功績を残したい」と答えた。しかし、曾皙( そうせき )だけはこう言った。「私は春の日に友人たちと川辺で水浴びをし、歌を歌いながら家に帰りたい」。これを聞いた孔子は微笑みながら、「私は曾皙の考えに賛成だ」と言った。この言葉には深い意味がある。それは現実逃避ではなく、曾皙が持つ心の平穏や愛情、人との調和を孔子が評価したからだ。教育とは、人々に競争させるためのものではなく、それぞれが自分自身の本当の願いや善意を見つける手助けをするものだ。それがどんなささやかな夢でも、人との絆や喜びに満ちていれば、それで十分価値がある。
さらに、子貢が「私はよく貧しい人々に寄付している」と自慢したとき、孔子はこう諭した。「仁者とは、人を愛する者だ。ただ物を与えるだけではなく、その人たちの気持ちや状況を本当に理解し、心から気遣っているだろうか?」。この言葉は私たちにも教えてくれる。仁とは単なる物質的な支援ではなく、命そのものへの深い愛情と責任感から生まれるものなのだ。
人は生まれながらに善良
「人の初め、性は本善なり(人は生まれながらに善良である)」これは中国古代の啓蒙教育書『三字経』の中で最もよく知られた一節であり、私たちにこう教えている。子どもは生まれながらにして善良である、と。教育の真の使命は、成功者を作り上げることではなく、この生まれ持った善良さを守り育むことである。
古代の教師たちは、単に知識を教えるだけではなく、「道を伝え、学問を授け、疑問を解く」ことを使命としていた。では、何の「道」を伝えていたのか。それは仁徳の道であり、生きる方向性であり、人としてどうあるべきかという道理である。
教師とは、単なる知識の運び手ではなく、子どもの人生における意味を導く案内人、道しるべのような存在であるべきだ。真の教育とは、競争力を養うだけではなく、子どもが善良で徳のある人間になる方法を理解させるものでなければならない。
現代の反省「私たちは何を教え、子どもたちは何を失ったのか?」
今日の教育はどうなっているのか?
私たちは子どもたちに問題の解き方を教えているが、自分の心の悩みや葛藤をどう解決するかは教えていない。
勝つ方法を教えているが、負けにどう向き合うかは教えていない。
自分をどうアピールするかは教えているが、他人をどう思いやるかは教えていない。
教育現場から「道徳」や「人間らしさ」への信頼が失われ、それとともに子どもたちへの忍耐や優しさも失われている。もし子どもが心の中で助けを求めているのに、私たちがただ成績表しか見ていないとしたら、その子を救うのは誰なのだろうか?
「愛と善良さ」を教育の中心に取り戻す
今こそ、古人の知恵を再び手に取るべき時かもしれない。
すべての教師が、自分は善良さを守るために教えているのだと思い出すこと。
親が、成功よりも「寄り添い」と「理解」のほうが追求する価値があると信じること。
社会が子どもたちに、泣くことも迷うことも、そして再出発することも許される空間を与えること。
真の教育者とは、どれだけ多くの「成功者」を生み出したかではなく、どれだけ多くの子どもたちが転んだときに再び立ち上がり、この世界で生きる価値を信じられるよう手助けしたかで評価されるべきだ。
子どもの心に明かりを灯そう
子どもは誰もが一つの灯火のような存在だ。私たちができることは、その灯火をしっかりと灯してあげること。そして、子どもたちが健やかに成長できるよう見守ることだ。
どうか、子どもが心を閉ざし、離れていき、希望を失ってしまう前に気づいてほしい。今日から、私たちは昔ながらの教育の知恵を見直し、本当に大切なことに立ち返ろう。人の善良さを信じ、思いやりの心を育み、一緒に成長を見守り、優しく接することを忘れないようにしよう。
社会を冷たく利己的なものではなく、温かく思いやりに満ちた場所に変えていこう。それぞれができる形で、子どもの心に明かりを灯してあげよう。そして、本来純粋で優しい子どもたちの未来を守るために、一緒に手を取り合おう。











 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




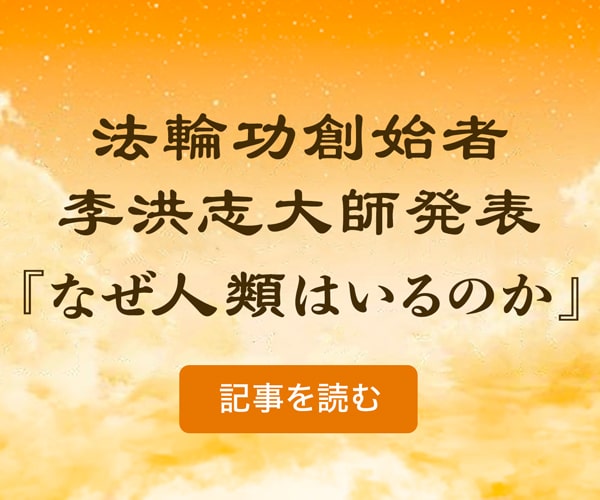
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。