2025年4月1日、インターネット上の誹謗中傷や権利侵害への対応を強化するための改正法「情報流通プラットフォーム対処法」(通称 情プラ法)が施行された。この法律は、SNS事業者に対し、被害者からの投稿削除申請への迅速な対応を義務付けるものである。一方、政府による検閲など「言論統制」につながるとして懸念の声も上がっている。
背景と目的
SNS上での誹謗中傷は深刻な社会問題となっている。匿名性を利用した悪質な投稿が後を絶たず、多くの人々が名誉毀損やプライバシー侵害といった被害に苦しんできた。これまでの法律では、削除申請窓口が不明確であったり、申請後の対応が遅れるなど、多くの課題が指摘されていた。このような状況を改善するため、政府は昨年5月に情プラ法を成立させ、今年3月にガイドラインを公表し、施行を1か月前倒しして本日から運用を開始した。
村上誠一郎総務相は、2025年2月18日の衆院総務委員会で、SNS上の誹謗中傷問題に関して次のように述べた。「表現の自由のもと、主張は自由に行われるべきでありますけれども、その主張の是非に関わらず人を傷つけるような誹謗中傷は絶対に許されないと考えております」
改正法の主な内容
情プラ法では、SNS事業者に以下の義務が課される。
1. 削除申請窓口の整備
被害者が投稿削除を申し出る窓口を設置し、その情報を公表すること。
2. 迅速な対応
削除申請を受理した場合、7日以内に調査・判断し、その結果を被害者に通知すること。
3. 透明性の確保
削除基準や運用状況を年1回公表すること。
さらに、違反した事業者には最大1億円の罰金を科す。特に海外事業者には、日本語で対応可能な窓口設置が求められるなど、日本国内での利用者保護を強化している。
言論統制につながる懸念
情プラ法を施行したことにより、SNS上の誹謗中傷への迅速な対応が義務付けられる一方で、政府による言論統制につながるのではないかという懸念が根強く存在している。
この法律は、被害者が投稿削除を申請しやすくするために窓口を整備し、事業者に7日以内の対応を求める内容となっている。しかし、批判的な声の中には、この制度が政府に都合の悪い意見を抑制する手段として悪用される可能性を指摘する。特に、本人以外の第三者による削除申請を認める点については、「表現の自由」を侵害する恐れがあると懸念している。
さらに、削除基準の曖昧さも問題視している。法律では違法情報や権利侵害情報への対応を求めているが、その具体的な基準は事業者側に委ねられている。このため、プラットフォーム事業者が恣意的な判断で投稿を削除する可能性や、選挙など政治的な場面で特定候補者への攻撃手段として利用するリスクも指摘している。
一部専門家は、この法律が「表現の自由」と「誹謗中傷防止」の両立を目指したものだと評価しつつも、その運用には慎重さが求められると述べている。特に、削除要請制度が透明性を欠いた場合、政府による検閲や統制につながりかねないとの懸念がある。
課題と期待
この法律施行により、被害者を迅速に救済する仕組みが整うことを期待している。一方で、実効性の確保や表現の自由とのバランスも課題として挙げられる。削除判断は事業者に委ねられるため、その運用が公平かつ適切であるかどうかが問われる。また、SNS事業者がどこまで迅速かつ積極的に対応できるかにも注目している。
政府は情プラ法について、「表現の自由を脅かすものではない」と説明している。しかし、実際にはSNS事業者への負担増や制度運用の不透明さなど、多くの課題が残されている。
情プラ法は、インターネット利用者全体の意識改革も促すものだ。事業者だけでなく、利用者一人ひとりが責任ある発信を心掛けることで、安全で信頼できるオンライン空間が実現するだろう。この新しい枠組みがどれほど効果的に機能するか、その成果に今後注視していく。



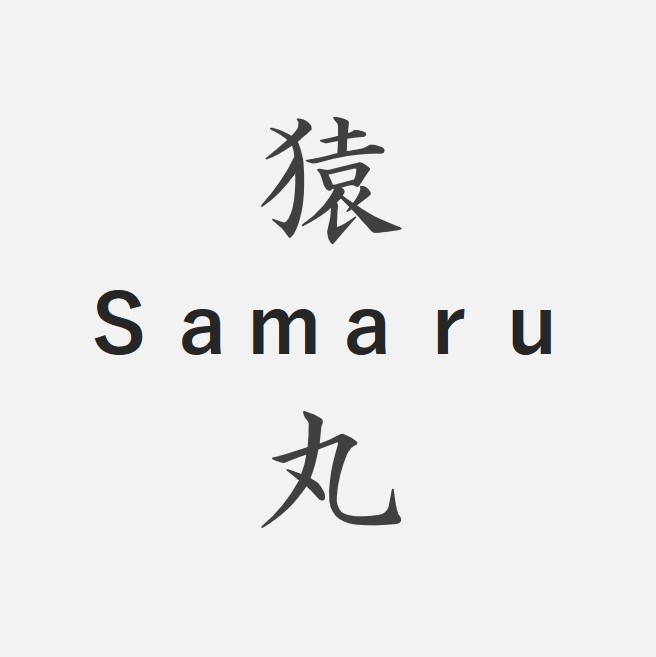




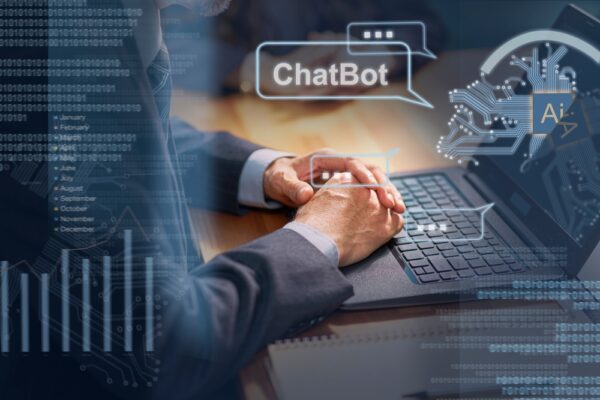

 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。