近年、抹茶の人気が世界中に広がり、抹茶ラテやさまざまなスイーツなど、緑豊かな抹茶製品が食文化のトレンドを象徴する存在となっている。しかし、この人気の高まりは、日本国内における抹茶の供給不足という深刻な問題を引き起こしていた。
2023年以降、多くの著名な日本の茶商が、抹茶粉の販売を制限し始め、市場の供給が厳しくなり、これにより、地元の消費者だけでなく、国際市場にも影響が出ている。
抹茶不足の主な原因は、世界的な需要の急増で、特に欧米市場では、抹茶が健康効果や日本文化の魅力から非常に人気を集めている。
日本農林水産省のデータによると、2024年には日本の緑茶(抹茶を含む)の輸出額が364億円(約2億4400万ドル)に達し、前年に比べて約25%増加し、5年連続で歴史的な高水準を記録した。
さらに、2024年の訪日観光客による消費額は8兆1千億円を超え、観光客の総数は3687万人に達した。これらはどちらも歴史的な新記録であり、抹茶の需要の増加をさらに後押した。
供給チェーンの圧力と政府の介入
需要が大幅に増加しているにもかかわらず、抹茶の生産は依然として、伝統的な生産方法と日本の茶業の構造的な問題に制約されている。抹茶は遮光処理された茶葉を粉砕して作られ、通常は年に一度しか収穫できず、そのため生産量は限られている。
同時に、人口の高齢化により、日本の農業は深刻な労働力不足の問題に直面している。2023年の日本の抹茶生産量は2008年の78%にとどまり、主な原因は製茶農家の高齢化と若者の後継者意欲の低下だ。
日本の茶葉産業の転換も急務となっている。国内では伝統的な茶葉の需要が徐々に減少しており、消費者の嗜好は飲茶製品などに移行しており、伝統的な急須で淹れる煎茶市場は継続的に縮小してきていた。
この問題に対応するために、日本の農林水産省は2025年度から、茶農家に対して一般的な「煎茶」から抹茶の原料である「碾茶」(てんちゃ)への生産のシフトを促す計画を立てており、この施策は2024年春の基本方針の改訂に盛り込まれた。
日本政府はこの戦略を通じて、抹茶製品に対する世界市場の高い需要を活用し、輸出を強化するとともに、国内の茶農家の経営を支援したいとの計画だ。
影響と未来の展望
供給不足のため、一部の有名な茶商は長期的な取引先に優先的に供給を行い、寺院や神社、伝統的な茶道関連機関の需要が影響を受けないようにしている。
例えば、京都の丸久小山園は2023年10月から小売を制限し、長期顧客への供給を確保している。京都に本店を構える日本茶専門店の一保堂茶舗は原材料費の上昇に応じて価格を引き上げた。
抹茶不足の影響は世界市場にも広がっている。オーストラリアのシドニーにあるSimply Native茶店は、2023~24年の間に抹茶の販売量が5倍に増加し、購入数量を制限せざるを得なくなったと述べている。
さらに、市場の需要が引き続き高まる中、多くのソーシャルメディアインフルエンサーが、自らのブランドの抹茶製品を次々と発表している。例えば、YouTubeのブロガーであるエマ・チェンバレン氏やアシュリー・アレクサンダー氏は、2024年に日本の静岡産の抹茶製品を発売した。
抹茶不足は、世界市場の需要と日本茶産業の供給との間の矛盾を反映している。今後、日本茶産業は生産モデルをさらに調整し、生産効率を向上させる必要がある。また、政府の政策支援を通じて、安定したサプライチェーンと持続可能な発展を確保することが求められている。
(本記事は、ブルームバーグ社と京都新聞の関連報道を参考にした)










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




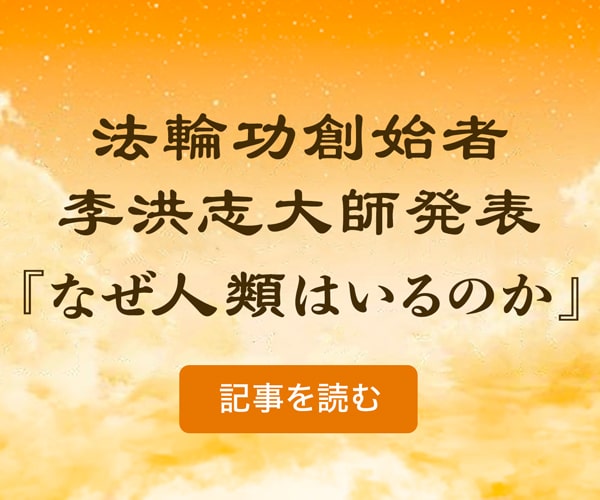
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。