2025年4月1日、日本政府は、感染症対策の強化を目的として、「国立健康危機管理研究機構(JIHS)」を正式に発足させた。この新機構は、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合し、感染症危機への迅速かつ科学的な対応を目指ざす。
厚生労働省の福岡資麿大臣は、記者会見で、
「初動対応の強化や地方自治体、国内外の関連機関との連携を通じて、感染症危機管理体制を充実させる」
と、述べた。JIHSは、平時から感染症の発生状況を監視し、情報提供に努めるとともに、有事には迅速な調査・分析を行い、政府に科学的知見を提供する役割を担うとした。
NHKによると、福岡厚生労働大臣は、閣議のあとの記者会見で、
「新型コロナ感染症の流行を踏まえ、引き続きさまざまな課題に対応していく必要がある。設立を契機に、地方自治体や国内外の専門機関などとより一層連携を深め、わが国の感染症危機管理体制を強化し、次なる感染症危機への備えを着実に進めていきたい」
と、述べた。
前回のパンデミックでは、突発的な感染症の発生によりワクチン開発の迅速化が求められ、安全性の検証が十分に行われなかったと指摘されており、日本政府の対応にも課題が見られ、次回のパンデミック時には、同様の問題を繰り返さないための制度設計が求められた。
新型コロナウイルス流行時、日本ではmRNAワクチンの接種が推奨されたが、インフォームド・コンセント(十分な説明と同意)が不十分であったとの指摘があり、接種者に対するリスク説明が不足し、心筋炎やアナフィラキシー(アレルギー反応の中でも特に重篤な全身性の即時型アレルギー反応のこと)などの副反応がが報告されたにもかかわらず、十分な情報提供が行われなかった。この結果、健康被害救済制度が報告されたにもかかわらず、十分な情報提供が行われなかったため、この結果、健康被害救済制度が前例のない規模で運用され、多くの遺族や被害者が政府に対し、賠償を求める訴訟を起こす事態となった。
JIHSは「日本版CDC」として期待されているが、その役割は、単なる感染症対策にとどまらず、国民の信頼を回復することも重要であり、そのためには情報開示の透明性が求められた。
日本政府は、新型コロナウイルス感染症対策としてmRNAワクチンの接種を推進してきたが、その過程で情報の透明性が欠如していたとの批判がある。特に、厚生労働省は国会議員や研究者からの質問に対し、接種後の健康被害について「ワクチンとの因果関係は認められない」「安全性は確認されている」との回答を繰り返し、具体的な根拠を示さなかったことが問題視されていた。
また、日本のワクチン接種政策に関するファイザー社との購買契約の詳細についても、国会議員の質問に対し明確な回答がなされず、不透明性が指摘されている。
厚生労働省は、副反応疑い事例を収集し公表しているが、因果関係については明確な結論を示していない。
接種後に、報告された死亡事例や重篤な副反応に関して、制度が開始された1977年2月からの47年間で認定された健康被害の件数は3680件、認定死亡者数は158件だったのに対し、新型コロナワクチンによる健康被害の認定死亡者数は818件と、5倍以上の件数となっていた。それにもかかわらず、政府は、ワクチン接種後の健康被害との因果関係を明確に認めず、ワクチン接種の推進を継続した。この対応には多くの疑問が寄せられていた。
今後、JIHSが感染症対策の司令塔として機能するためには、科学的根拠に基づいた政策立案と、国民への十分な情報開示が不可欠だろう。







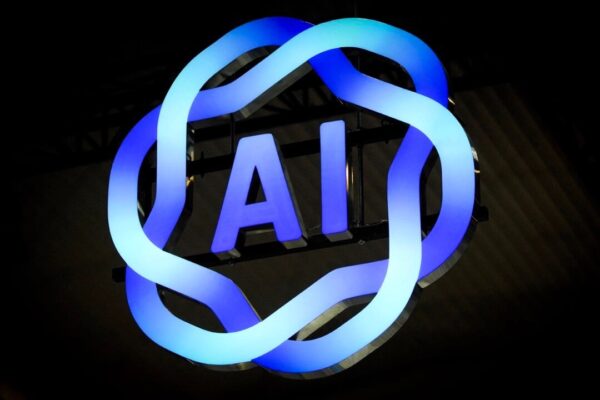


 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。