米司法省は、中国人留学生がドローンを使ってバージニア州の造船所を撮影した事件で、スパイ防止法に基づく異例の訴追を進めている。米海軍は同造船所で原子力潜水艦を建造中だ。日本でも護衛艦「いずも」がドローンで撮影され動画が中国のSNSに拡散されており、軍事施設の対ドローン対策が喫緊の課題となっている。
米海軍の造船所をドローンで撮影し、今年1月にスパイ容疑で逮捕されたのはミネソタ大学の博士課程に在籍する中国人留学生の施鳳雲(シー・フォンユン)だ。米メディア・ワイヤードが5月末に報じた。
施被告は1月5日、バージニア州のハンプトン・ロードの造船所周辺でドローンを飛行させた。不審に思った住民が警察に通報したところ、被告はドローンを現場に放置したまま立ち去った。
FBIが押収したドローンからは、バージニア級原子力潜水艦の建造する造船所の映像が発見された。施被告は、造船所とその周辺300メートル以内の上空でドローンを無許可で飛行させた容疑で逮捕され、スパイ活動に関する法律に基づき、6件の軽犯罪で起訴された。
捜査当局は、中国共産党との接触の有無など背景についての調査を進めている。被告が中国の情報機関との関係を認めれば、より重大な法律違反に問われる可能性もある。有罪となれば、各容疑で最長1年の禁固刑が科される可能性がある。
日本でも「いずも」空撮
3月末、中国のSNS上に海上自衛隊の護衛艦「いずも」の空撮映像が投稿され、物議を醸した。防衛省は1か月以上の調査の末、映像はCGではなく実際の撮影である可能性が高いとの見解を公表した。
「世界首席無人機盗撮芸術家」と称する投稿者は3月末、中国の動画SNS「BiliBili」の自身のアカウントに、横須賀港に停泊中の「いずも」を撮影したとする動画をあげた。動画には艦番号や船体構造、レーダーなどの装備が鮮明に写し出されていた。動画はすぐに削除されたが、X(旧Twitter)上でも同様の投稿があり、拡散された。
「いずも」は本来、大型の「ヘリコプター搭載護衛艦」だが、垂直離着陸が可能なF-35Bを搭載するための改修の最終段階にある。インド太平洋地域における中国との戦略的・軍事的緊張の高まりを受け、改修されているいずもは日本防衛の要であり「虎の子」とも例えられている。
このアカウントには、同じ横須賀基地の空母エイブラハム・リンカーンやアーレイ・バーク級イージス艦などの米艦艇の映像も複数アップロードされていた。
米軍機関誌の星条旗新聞の取材に応じた米海軍横須賀基地広報担当は、米海軍犯罪捜査局(NCIS)が「(画像の)信憑性を調査している」としつつ、「セキュリティ上の問題は生じていない」と答えた。
神奈川県警は自衛隊側と対応を検討し、小型無人機等飛行禁止法違反容疑を視野に捜査を開始。こうした報道を受け、このアカウントは「日本の警察が私を逮捕したがっている。中国にいる私はとても怖い」「わたしの行動は中国政府と関係ない」などと述べている。
大紀元はこのアカウントに連絡したが、記事発表までに回答は得られなかった。
軍事ジャーナリストの山田敏弘氏は自身のインターネット番組で、今回の投稿者について、当局の工作員ではない可能性が高いと分析。「本物の工作員なら、日本の防衛態勢の隙を公にするよりも、情報を秘匿しておく方が中国にとって利益」との見解を示した。また、機密施設における不審ドローンの電波を遮断するシステムや装置の導入を提言した。
いっぽう、「工作員」ではなくとも、中国当局はデータを把握しているとの指摘もある。ある警察関係者は大紀元の取材に対して、GPSを使用する中国製ドローンならば中国の衛星通信システムでドローンの移動情報が把握できると指摘。当人が工作員であろうがなかろうが、ドローンは当局に情報を送受信していると述べた。
「自由」が阻む防衛
本件では、日本の重要施設における警備の不備が露呈した。木原稔防衛相は記者会見で、「今回の件を非常に重く受け止めている。無人航空機の探知がより困難になる可能性があるため、基地の警備を徹底していく」と述べた。
ドローン撮影者を起訴する場合、ネックとなるのが自由権との衝突だ。過去に米国では公道から基地を撮影した地方新聞の記者を警備員が拘束した事件で、「表現の自由に対する妨害」だったとして警備員側に1.8万ドルの罰金が命じられたケースもあった。
施容疑者のケースでは、第二次世界大戦時代に定められた反スパイ法に基づく起訴となっているが、撮影行為をスパイ容疑として起訴することは米国でも極めてまれだ。
専門家は、施容疑者のケースは反スパイ法をドローン撮影に適用した初の起訴で、起訴後の展開は不透明だと指摘する。
日本ではどうか。ドローン飛行が問題化した平成28年に「小型無人機等飛行禁止法」が制定され、自衛隊や米軍基地、首相官邸、原子炉、その他「テロ攻撃やスパイ活動の標的となりうる重要施設」の近くで、無人航空機を許可なく飛行させることは禁止され、違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる。
いっぽう、沖縄県では現地紙が同法に対して「空からの目をふさぎかねない」「目隠し法」と反発しており、憲法の保護する言動の自由をドローン使用規制に反対する理由づけとしている。
電波を発せず探知できないドローン
ドローンには2種あり、衛星通信にとらわれずプログラミングで自律飛行するドローンは電波を発しない。このため、現在の対応では探知できない可能性がある。参院外交防衛委員会で榛葉賀津也議員(国民民主)はこの点を指摘し、防衛省に早急な対策を求めた。
防衛省は「高度な探知能力を持つ機器の導入を検討している」とし、特殊な対ドローンレーダーや対UAVシステムを導入する可能性を示した。後日の衆院外務委員会では、鬼木誠防衛副大臣が、ドローンを発見次第、妨害電波で強制着陸させるなどの対策を進めていく方針を語った。
英字紙「日経アジア」によると、小型ドローンは時々「鳥と間違えられる」ことがあり、高速で機動性の高いドローンは「継続的に追跡できない」可能性がある。
ロシアとウクライナの戦争では、双方ともドローン攻撃への対応に苦慮している。ドローンはミサイルよりも安価で、民間市場で入手できるため、非対称戦では無視できない戦力となる。
ドローンの小型化・高性能化が進む中、軍事機密の漏洩リスクに各国が神経をとがらせている。安全保障の観点から、法規制や警備体制の一層の強化が急務となっている。








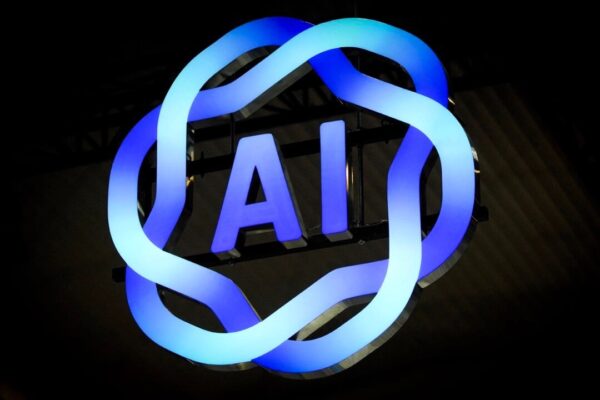

 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。