まもなく2023年を終えようとする今、まさに「津波のようだ」と形容されるほどの疫病の大波が、世界のなかで、なぜか中国だけに襲いかかっている。そのようななか、集団感染リスクが特に高い学校に、ゼロコロナ時代を代表する「白服の防疫要員(大白、ダーバイ)」がまた現れた。
今月4日、中国の教育部が全国の学校に対して「新型コロナウイルス感染症への対策を講じるよう」求める通達を発した。
ウイルス感染症の患者が爆発的に増えた病院では、これまで「マイコプラズマ肺炎」などの病名を診断結果としてきた。しかし、もはや隠蔽は効かず、新型コロナであることを認めざるを得なくなった現在、まさに手の平を返すように、新型コロナ対策へ転換したことになる。
「忌まわしい記憶」の再来
中国のネット上では、各地の学校に「大白」がやってきて殺菌消毒の作業を行う様子を映した画像や動画が数多く投稿されている。それはまさしく、全ての中国人にとって思い出したくもない「忌まわしい記憶」の再来となった。
今から1年前の2022年12月7日。中国共産党がコロナ感染症を「ゼロにせよ」と命じて、約3年にわたって狂気のように進めてきた「ゼロコロナ(清零)政策」は事実上、継続不可能になった。
ゼロコロナ政策は、その効果を検証されることなく、終り方も全く明確でないまま、民衆の巨大な恨みだけを残して消えたのである。
その前月である11月から、民衆が各地で白い紙を掲げて街頭へ出る「白紙運動(革命)」が続き、当局のゼロコロナ政策に対する反発は極限に達しようとしていた。
その大きなきっかけは、新疆ウルムチで11月24日に起きた集合住宅の大規模火災であった。
ゼロコロナ政策により、建物の鉄扉が封鎖されていたため、迅速な救助や消火ができなかったことが被害を拡大させた最大の原因である。当局発表の犠牲者数は「10人」だが、その数字を信じる中国人はいない。民間では「子供もふくむ44人が、生きながら焼け死んだ」という話が伝わっている。
いま火災当時の映像を見ても、身の毛がよだつ。激しく燃える建物のなかから「開けて、助けて!(開門、救救我們)」と絶叫する、火のなかの居住者の声が聞こえるのだ。
ゼロコロナ政策が終わった1年前のその時から、街角の至る所に設けられていたPCR検査のブースは次々と閉鎖された。大量の「大白」の要員は、突然にして「用無し」となり、給料もろくに支払われないまま解雇された。
その直後には、白服の「大白」たちが、未支給の給与を求めて街頭で抗議デモを行う様子も見られたが、市民は全く同情せず、冷ややかに眺めるだけだった。
それもそのはずであろう。市民は、たとえ職務上の行為とはいえ、これまでに「大白」がやったあまりにも極端で暴力的な防疫措置について、憎悪の念さえ抱いていたからだ。
玄関ドアを破壊して、侵入する「大白」
米政府系放送局ラジオ・フリー・アジア(RFA)は7日、「ゼロコロナ終了1周年」をテーマに、中国で3年近く続いたゼロコロナの「忌まわしい記憶」を記録したシーンをまとめた。
室内の消毒のため、玄関ドアを破壊してでも侵入してくる「大白」。強制的な隔離政策。山積みにされた「遺体袋」。銃をもつ警備要員に対して、市民が「誰に向けて銃をもっているのか?」と質している。
どれもが目を疑うばかりの光景だが、これが1年前まで、中国で現実にあったことなのだ。
「あの悪夢のような日々が、再び来るのか?」。この懸念は、いまや中国人の誰もが抱いていることだろう。
ともかく2023年12月の今、再び「大白」は現れてしまった。その効果がほとんどなかったことは前回の経験で明白なはずなのだが、また同じことをやろうとしているとしか思えない。
そもそも、病原ウイルスは細菌ではない。しかし、白い防護服の「大白」が消毒剤を大量に噴霧している様子は、一般的な食中毒菌などを対象とする防疫にはなっても、中共ウイルス(新型コロナウイルス)の感染予防にどれほど有効であるのか。
その答えを誰も知らずに、それをやっている。それで「大白」は臨時の職を得られたし、消毒剤や防護服のメーカーはまた儲かる。地方行政も、それで上から言われた任務を遂行したことにできるのだ。
行政側の誰もが無責任になっており、誰もがその結果に目を向けようとしない。中国の民衆は、ただ必死で、気も狂いそうな今日を生きようとしている。
(ラジオ・フリー・アジア(RFA)の動画。ゼロコロナ政策期間中に続いた「大白」の防疫措置。室内の消毒のため、玄関ドアを破壊してでも侵入してくる。強制的な隔離政策に、山積みになった「遺体袋」。銃をもつ警備要員に対して、市民が「誰に向けて銃をもっているのか?」と質している)
河南省

黒竜江省

山東省










安徽省








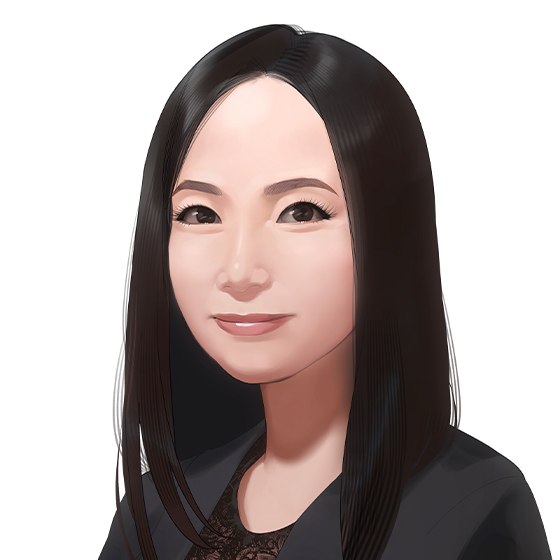







 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。