台湾人のビジネスマンが、我先にと中国大陸へ「出稼ぎ」に行っていた時代は、すでに終わった。
中国で30年以上のビジネス経験を持ち、中国側による浸透の手口を知り尽くす台湾商人の吳丹文(仮名)さんは、エポックタイムズの取材に応じて、次のように語った。「もはや目を覚ます時だ。中国市場に対する一切の幻想を捨てよ!」。
多くの台湾商人が、中国から撤退中
米中貿易戦や中国でのビジネス環境の悪化などをきっかけに、ますます多くの台商(台湾商人)が中国からの撤退を選択している。
「中国に対して、いまだに幻想を抱いている台湾人に私は言いたい。いいかげん目を覚ましてほしい。どこの国へ行ってもいい。どこへ行っても(ビジネス環境は)中国より良いからだ。中国に行ってしまえば、そこから抜け出ようとしても、もう出られない可能性がある」
「中国でビジネスをするにあたって、我々には多くのレッドライン(超えてはならない一線)がある」という呉さんは、さまざまな思いがあってエポックタイムズの取材を受けるかどうか、しばらく悩んだという。それでも、自分が伝えるべきことを伝えたいと心に決めた。以下は、呉さんのインタビューの概要である。
呉さんは「近年では、感染症対策をめぐる封鎖、企業に対する厳しい取り締まり、米中貿易戦争、若者の失業率の急上昇、輸出や内需の不振、不動産業界の低迷などが重なり、中国経済は今、非常に悪くなっている」として、ここ数年、自身が関係する中国でのビジネスを縮小し始めている。
はじめは「友好」実は「とことん利用」
それでも、台湾商人が中国で本当に悩まされるのは、ビジネス環境の悪さではなく「文化の壁」だと呉さんはいう。
この「文化の壁」とは、伝統中国が擁する輝かしい文明のことではなく、中国共産党のもとで、腐肉を蝕むように培養された「悪しき慣習」と言ってもよい。とにかく悪事に引き入れて「共犯者」にしてしまえば、あとは言いなりになる、と彼らは考える。ひとつ弱みを握られたら、中国側の思う壺である。
呉さんによると、台商(台湾商人)が中国で直面する最大のリスクは「中国当局による、長期的な浸透工作だ」という。中国当局は、さまざまなルートを通じて企業機密を盗もうとする。そして台湾人のビジネスマンを誘い込んで、最終的に「中国側の言いなりになるスパイに仕立ててしまう」というのだ。具体的な手口は、こうである。
「初めて中国へ行ったとき、手配された接待役の人たちは、我われ台湾人に対して本当に友好的だった。ところが何年かすると、その中国人の友好的な態度が、表面的なものに過ぎないことに気づく。彼らは、裏では台湾人を監視する任務があったのだ」
「中国側は、台湾商工会議所などの組織に手先を潜り込ませて、台湾商人に近づけさせる。打ち解けやすい酒の席などを利用して、ごく普通の家庭や養生(健康法)などリラックスできる話題のなかから、彼らは突破口を探ってくる」
中国側は、ターゲットを必ず「落とす」
とくに中国当局は「金と女を使って、台湾商人を落とすのを得意としている」と呉さんは言う。
その人間に利用価値を見出せば、中国側は必ず「落とし」にかかる。その人間が中国側の手に落ちれば、次には「任務遂行」を求めてくるとして、中国側の陰謀に警戒を促した。
「中国側は、台湾人を通じて台湾の商業技術を盗むとともに、中国共産党に対する台湾社会の認識を変えさせようとする。彼らは台湾の国防や政界に影響力のある人物と接触できることを望んでいるが、それに限らず、中国側はどんな情報にも興味を示す。その結果、台湾には中国市場を公に称賛する親中派の台湾商人が多くなってしまった」
呉さん自身は、中国に浸透されると最終的に台湾に戻れなくなると考えて、できるだけ「中立的な」経営方針でやってきた。そんな呉さんの会社は近年、中国側に「協力的でない台湾商人」のカテゴリーに分類されたという。
それ以来、呉さんの会社は、中国側からさまざまな嫌がらせを受けるようになった。多くのトラブルに巻き込まれ、想像を絶する額の損失を出したという。
「中国に行く必要など、全くない」
「中国当局が、台湾商人を懐柔するのはいとも簡単なことだ。しかも、彼らはいつでも台湾商人を突き落とすことができる。台湾商人は、中国にとってどんどん価値のないものになってきている。だから、今もなお中国市場に幻想を抱いている人がいるとすれば、本当に、もういい加減目を覚ますべきだ」
そう述べる呉さんは「中国は無法地帯だ。どんなに努力してビジネスを大きく展開したとしても、全てが一夜にして水泡に帰す可能性がある。中国に行く必要など全くない」として、中国でビジネスをすることが、いかにハイリスクを伴うかを繰り返し強調した。
呉さんが実体験から警告を発するように、言語上の障害が全くない台湾商人であっても、今の中国は「正常なビジネス」ができる環境ではないという。
日本の対中ビジネスを行う各企業は、この提言をどう受け止めるのか。50年前の、盲目的な「日中友好」の時代でないことは言うまでもない。



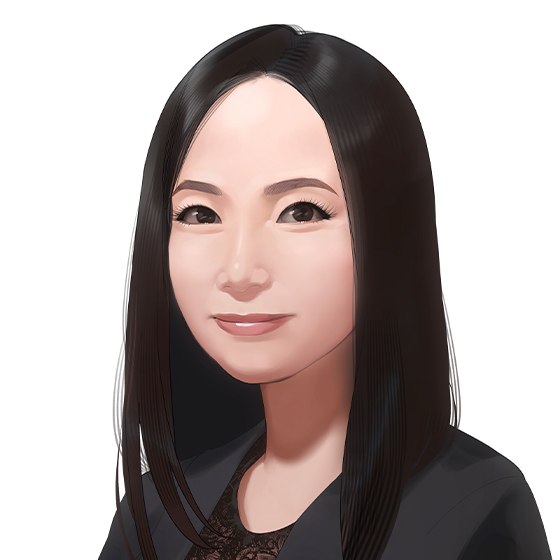







 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。