前々回のコラムで、文系知識人には、自分の中で先に結論が決まっており、その結論に沿う資料だけを探してきて、それを論拠に主張する傾向があると述べた。今回は、この点についてもう少し掘り下げてみたい。
この世の中、仕事によっては先に決まった結論に合わせて議論をしなければいけないことがある。弁護士であれば当然、依頼主に有利な結論となるように議論を組み立てねばならない。しかし、文系知識人が全てそういう仕事に就いているわけではない。にも拘らず、結論を先に決めるような態度をとることが多いのはなぜか。今の学校教育における文系科目の教え方に原因があるのではないかというのが私の見立てである。
私は高校生の頃、理系科目よりも英語や国語などの文系科目の方が得意だった。それでも理系を選んだのは、社会科で教えられる内容や国語における小説を題材にした試験の出題に納得いかないことが多かったからである。その非論理性を嫌って理系に進んだ面がある。
具体例を挙げよう。世界史を選択した人なら、ローマ帝国の五賢帝のことはよく知っているはずだ。私はこの五賢帝時代を、世襲ではなく優秀な人を養子にして次の皇帝にしたから栄えたと習った。五人目のマルクス・アウレリウスは自分の息子を次の皇帝にしたので、ローマ帝国は衰退を始めたと。私はこれを聞いた当時、人間の性としてそんなきれいな話はありえないと思って納得できなかった。
この違和感は大学生になっても頭の片隅に残っていた。そこで、南川高志先生の著作をはじめ、五賢帝時代に関する本を何冊か勉強してみた。それで分かったのは、この時代に少年愛が流行っていたことである。実際、トラヤヌスとハドリアヌスには少年愛の性癖があったと伝えられる。そうした背景もあり、五賢帝のうちの四皇帝には後継者となる実子がいなかった。それを知って、世襲が行われなかった理由を漸く納得できたことをよく覚えている。
日本史についても同様の疑問は多数あった。例えば、豊臣秀吉がバテレンを追放したのは、自分より偉い神の存在が許せなかったからだと教わった。私はそれを聞いて、大君から関白の称号を受けていることに大きく矛盾すると思った。これも後に、日本人奴隷を売買していたことがバテレン追放の理由だったという説明を見つけ、漸く納得できた。
江戸時代にキリスト教を禁止したのに、なぜキリスト教国オランダとの交易は許したのかも、歴史の授業では納得のいく説明を与えない。倉山満氏の著書で、それがカルヴァンの予定説と関係している(神に救済されるか否かは予め決まっているので積極的に布教しない)と知ったときには目から鱗だった。同じく江戸時代に、新井白石や松平定信の倹約政策が肯定的に論じられるのに、それで世の中が一向に良くならない理由も全く分からなかったが、上念司氏の著書『経済で読み解く日本史』を読んで、実はそれらの政策が失敗だったことを学んだ。
学校ではなぜこうしたことを教えないのか。結局、歴史科が事実や論理よりもイデオロギーを重視した科目になってしまっているからだろう。五賢帝時代は優秀な後継者を選んで継がせたから栄えたという話は、ソ連や中国の共産党指導体制への礼賛に結び付く。日本人奴隷の話は、日本人は常に加害者であって被害者たりえないとする左翼イデオロギーの物語と対立する。新井白石や松平定信の否定は、緊縮を善とする原始共産制・農本主義に反する。こうして歴史をイデオロギーに寄せた物語にすると、当然論理的つながりはおかしくなる。そんな歴史を学ばされれば、自ら論理的に考えようとする人が歴史嫌いになるのは当然である。
これと同じ種の問題は国語科にも見られる。みなさんは新美南吉著の『ごんぎつね』をご存じだろうか。私はこの作品を小学校の国語の授業で習った。今でも一部の小学校の国語教科書に採録されている。だいぶ前の話だが、この作品が息子の教科書に載っていたので、久しぶりに読んで大きな衝撃を受けた。私が記憶している話と全く違うのである。
もちろん、作品自体は改変されていない。しかし、大人になって自分で解釈して読むと、学校で習った物語とは全く違ったメッセージ性をもつ作品だと気づいたのである。おそらく多くの人は、この物語を可愛そうなごんの話だと習ったはずだ。
私の記憶はこうだった。いたずら好きの狐のごんが兵十のうなぎを盗んだ。そのうなぎは兵十が死にそうな母に食べさせるためのものだった。兵十の母はうなぎを食べられないまま死んでしまった。そのことを後で知ったごんは、お詫びのため毎日隠れて栗や松茸を兵十の家に置いていった。ある日、自分の家にごんがいるのを見つけた兵十は、またいたずらにきたと思って、ごんを銃で撃った。撃った後、栗を見つけた兵十は、それを持ってきたのはごんだと気づいた。
これだけを聞くと、可哀想なごんの話だと思うだろう。私の聞いた範囲では、ほとんどの人は私と同じようにこの物語を記憶していた。しかし、あらためて読み直すと、ごんが撃たれる前に、私の記憶にない次のシーンがあったのである。
「そうそう、なあ加助」と、兵十がいいました。
「ああん?」
「おれあ、このごろ、とてもふしぎなことがあるんだ」
「何が?」
「おっ母が死んでからは、だれだか知らんが、おれに栗やまつたけなんかを、まいにちまいにちくれるんだよ」
「ふうん、だれが?」
「それがわからんのだよ。おれの知らんうちに、おいていくんだ」ごんは、ふたりのあとをつけていきました。
(中略)
「さっきの話は、きっと、そりゃあ、神さまのしわざだぞ」
「えっ?」と、兵十はびっくりして、加助の顔を見ました。
「おれは、あれからずっと考えていたが、どうも、そりゃ、人間じゃない、神さまだ、神さまが、お前がたった一人になったのをあわれに思わっしゃって、いろんなものをめぐんでくださるんだよ」
「そうかなあ」
「そうだとも。だから、まいにち神さまにお礼を言うがいいよ」
「うん」
ごんは、へえ、こいつはつまらないなと思いました。おれが、栗や松たけを持っていってやるのに、そのおれにはお礼をいわないで、神さまにお礼をいうんじゃア、おれは、引き合わないなあ。
このシーンが存在する以上、この作品は単に「可哀想なごんの話」であるとの解釈は成立しない。最初はお詫びのつもりでも、次第に傲慢な気持ちになる人間の習性への戒めの話と解釈するのが順当である。ごんが最後に見つかって撃たれたのは、自分の善行だと知って欲しくなったからだと考えるべきだろう。筆者が可哀想なごんの話を書きたかったと理解するのは、わざわざこのシーンを描写したことと論理的整合性がとれない。私が上記シーンを忘れていたのは、「可哀想なごんの話」という先生の教えと整合しないので、認知的不協和を解消するため記憶から消し去られてしまったのではないかと思われる。
ごんきづねは童話であっても非常に深い作品である。その文学性を無視して、「一見悪い狐(人)も本当は優しいのだ」という左翼イデオロギーの色に染めて教えてしまうのでは、論理的思考能力だけでなく、文学を理解する力も育たない。
論理的思考の軽視は、国語の試験の出題にも見られる。これは、ある問題集で見た例である。森で熊が銃で撃たれて倒れ、その後に続く「森が泣いた」の表現の解釈を問う問題であった。一つの選択肢が熊の呻き声で、もう一つが銃声のこだまであった。私は致命傷を負った熊は大きな声を上げられないし、銃声は森に響き渡るほどの爆音なので、論理的に考えて後者だと思った。ところが正解は前者だった。なぜ前者が正解であるのかの論理的説明は解答の解説には一切なかった。これに限らず、小説を題材にした出題では、出題者の思い込みで正解を設定しているケースが少なくない。
論理的文章の出題ですら、ときどき正答が論理的に一意に定まらないケースがある。これまで私の著作は把握しているだけで7回大学入試に使われているが(今は赤本の著作権許諾の連絡が来るので情報が入る)、明らかに悪問が多いと思ったことが1回、若干疑問があると思った出題が1回あった。理系の出題の場合、少しでも多義性があると出題ミスとして大騒ぎになるが、国語についてはその種の多義性が許されてしまっているのである。
今、高校の国語の現代文が「論理国語」と「文学国語」に再編される話が浮上している。選択制になり、文学に触れない高校生が出てくることを危惧する声も大きい。私も高校生には文学も評論も両方読ませるべきだと思うが、文学を読むにも論理的思考の裏付けは必要である。改革すべきは、論理を無視して教師や出題者の勝手な解釈を押し付ける文系科目の教育の在り方である。そこを修正しない限り、論理的思考力をもつ文系人材を育成することはいつまで経ってもできないだろう。
執筆者:掛谷英紀
筑波大学システム情報系准教授。1993年東京大学理学部生物化学科卒業。1998年東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻博士課程修了。博士(工学)。通信総合研究所(現・情報通信研究機構)研究員を経て、現職。専門はメディア工学。特定非営利活動法人言論責任保証協会代表理事。著書に『学問とは何か』(大学教育出版)、『学者のウソ』(ソフトバンク新書)、『「先見力」の授業』(かんき出版)、『知ってますか?理系研究の”常識”』(森北出版)など。
※寄稿文は執筆者の見解を示すものです。
※無断転載を禁じます。

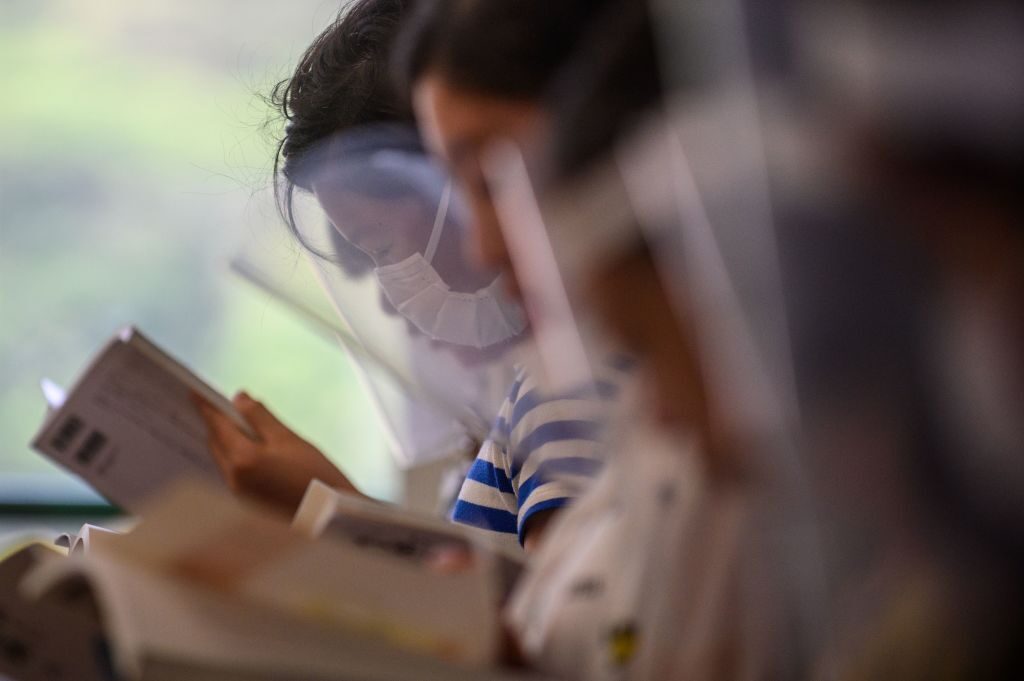

 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。