中医学では「春は肝を養う季節」とされています。春になると、女性は肝の気が乱れやすくなり、その影響で体調を崩すだけでなく、顔色がくすんで青黒くなったり、黄色っぽくなったりして、美しさが損なわれることもあります。しかし、古くから美しい女性は「花」にたとえられてきました。これは、花と女性に深い縁があることを示しています。さまざまな花茶を上手に取り入れることで、気血の巡りを整え、肝の気の流れをスムーズにし、本来の明るく血色のよい肌や、透明感のある美しさを取り戻す手助けとなるのです。
肝と脾のバランスが乱れると、顔色は青黒くくすんでしまう
女性の顔色が明るく赤みを帯びているかどうかは、肝と脾のバランスがとれているかどうかに大きく関係しています。中医学では、五臓は五行と対応しており、肝は「木」に属します。そして五行は五色にも対応し、「木」は「青」にあたります。そのため、肝の気は青色の性質をもちます。肝の気と血の流れが整っていれば、その色が顔に現れることはありませんが、バランスが崩れると「肝の青」が顔色に表れ、顔が青黒く見えるようになります。
同様に、五臓のひとつである脾(消化器系)は「土」に属し、土の色は「黄」です。脾の働きに不調が起こると、顔が黄色く見えるようになります。これは土の気が表面に現れたもので、脾胃に問題があるサインです。青黒さと黄ばみが混じったような顔色は、しおれた青菜のようで、女性の美しさを損なうだけでなく、心身の健康にも悪影響を及ぼします。気分が落ち込み、活力も失われてしまいます。
肝と脾の関係は「相克(そうこく)」、つまりお互いに影響し合い、制御し合う関係です。春は「木の気(木気)」が盛んになる季節で、これは肝の働きと関係が深いため、春は肝の気が乱れやすい時期でもあります。その結果、脾胃にも影響が及び、消化機能が低下し、肝脾のバランスが崩れてしまいます。
中医学では、肝は「血を蔵し、気血の流れを調節する」役割をもつとされ、女性は毎月の月経があるため、肝の気血の流れがスムーズであることがとても大切です。春の気候は肝の働きに影響を与えやすく、気血の巡りが乱れやすくなります。すると、脾胃の働きも弱まり、情緒が不安定になりやすくなります(抑うつや不安感)、さらに消化不良、食欲不振、気血不足といった状態が重なり、心身の健康や顔色にも影響を及ぼすのです。
そのため、血色のよい明るい顔色を保つには、肝の気血の流れを整え、肝と脾のバランスをとることが大切です。桜、バラ、ジャスミン、菊などの花には、気血の巡りを良くし、肝の気を整えて気分を明るくする作用があります。これらは肝と脾のバランスを整える効果があり、美肌づくり、肝のケア、情緒の安定、心と体の調和に役立ちます。
そこで、それぞれの花の効能に応じた花茶のレシピを紹介し、体質に合ったケアを通じて、明るく美しい顔色と、穏やかで快適な毎日を過ごすお手伝いをしていきます。
肝を整え美を育む、4種の花茶レシピ
1. 桜とバラの花茶(肝を整え、気血を巡らせる)

配合:乾燥桜の花 3g、バラの花 3g、クコの実 5g、種を取ったナツメ 2個
作り方:
- すべての材料を軽く洗い、カップに入れる。
- 90℃のお湯を注ぎ、フタをして5〜10分蒸らす。
- よく混ぜてから飲む。お湯を注ぎ足して2〜3回まで楽しめる。
効能:
桜の花は穏やかな性質で美容に良く、バラは気の巡りを良くし、ストレスを和らげて血行を促進。クコの実は肝腎を滋養し、ナツメは血を補い美容を助けます。これらを組み合わせることで、肝の気を整え、気血の流れを良くし、顔色を明るく整えます。
おすすめの人:
- 肝の気が滞り、イライラしやすい、月経不順のある方
- 顔色がくすみ、気血が不足している女性
注意点:
- 月経量が多い方や妊娠中の方は、バラに活血作用があるため、医師の指導のもとで使用すること。
- 体が熱を持ちやすい方は、クコの使用量を減らすとよい(以下同様)。
2. バラとジャスミンの花茶(肝の気を整え、脾胃を養う)

配合:バラの花 3g、ジャスミン 3g、陳皮 2g、紅茶 2g
作り方:
- バラ、ジャスミン、陳皮をぬるま湯で軽く洗う。
- カップに材料を入れ、紅茶を加える。
- 85〜90℃のお湯を注ぎ、5分ほど蒸らしてから飲む。
効能:
バラは肝の気を整え、ジャスミンは胃を温めて調える働きがあります。陳皮は脾の働きを助けて湿気を取り除き、紅茶は体を温め気を補います。消化を助け、緊張や不安を和らげ、顔色を明るくします。脾胃に湿気が多い場合は、炒ったハトムギや小豆を加えると、さらに効果的です。
おすすめの人:
- 肝の気が滞りやすく、胃が冷えやすく、膨満感・消化不良のある方
- 顔色がくすみ、肌にツヤがない方
注意点:
- 温性の素材が多いため、体が温まりやすく、寒がりの方に適していますが、体に熱がこもりやすい方は常用を避けること。
- 妊婦はバラを除いて飲むか、医師に相談してください。
3. 菊とクコの花茶(肝を冷まし、目を癒し、美肌に導く)

配合:杭菊花 3g、クコの実 5g、桑の葉 3g、蜂蜜 適量(飲用時に加える)
作り方:
- 菊、クコ、桑の葉をカップに入れる。
- 85℃のお湯を注ぎ、5〜8分蒸らす。
- お好みで蜂蜜を加えて飲む。
効能:
杭菊は肝の熱を冷まし、目をすっきりさせる作用があります。クコは肝腎を滋養し、桑の葉は熱を取り除きます。目の使いすぎ、肝火の高まり、肌のくすみやニキビが気になる方に適しており、肌を清らかに整えます。
おすすめの人:
- 夜更かしが多く、目が乾燥しやすい、肝火が強い方
- 肌が脂っぽく、ニキビやくすみが出やすい方
注意点:
- 陽気が不足している方、胃腸が弱く下痢しやすい方は使用を控える。
- 蜂蜜にアレルギーがある方や、小さなお子様は使用しないこと。
4. バラと龍眼の花茶(血を補い、美肌と潤いをサポート)

配合:バラの花 3g、龍眼(桂円)3粒、ナツメ 3粒、クコの実 5g
作り方:
- 龍眼は殻と種を除き、ナツメは切れ目を入れる。
- 材料をすべてカップに入れ、90℃のお湯を注ぐ。
- 蓋をして10分蒸らしてから飲む。
効能:
バラは気血を巡らせ、龍眼は心と脾を温め、ナツメは血を補って心を落ち着かせ、クコは肝腎を養います。血虚による冷え、顔色の悪さ、不眠などに効果があり、体を内側から温め、美しさを引き出します。
おすすめの人:
- 手足が冷えやすく、顔色が白い、不眠や物忘れがある方
- 気血が不足し、体力がない方
注意点:
- 全体的に体を温める効果が強いため、熱がこもりやすい方は控えめに。
- 妊婦の方はバラを含むため、医師の指導のもとで使用してください。
花茶を飲む際の注意点と購入時のポイント
これまで紹介した花茶に使われる花々ですが、アレルギー体質の方は飲用を避けてください。特にバラの花には血行を促進する作用があるため、妊娠中の方は必ず医師に相談のうえで飲むようにしましょう。
また、花茶を初めて飲む方は、体を慣らすために、使用する花の量を最初は半分、または3分の1程度に減らして試すのがおすすめです。無理なく体に合うかを確認しながら進めましょう。クコの実(枸杞)やナツメ(紅棗)の量についても、体質に応じて加減してください。体が熱を持ちやすい方や、湿気と熱がたまりやすい体質の方は、量を減らすか、使用を控えるとよいでしょう。
なお、桜の花などを使用する際は、必ず「食用」と明記されている、茶用として適した乾燥花を購入するようにしてください。
(翻訳編集 華山律)













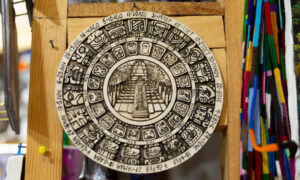










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。