2000年以上前の前漢の時代、翟方進(てき・ほうしん)という人物がいました。彼は幼い頃に父親を亡くしましたが、コツコツと勉学に励み、青年になると長安に移り住む決心をしました。翟氏の継母は、まだ幼さの残る彼を不憫に思い、一緒に長安へ上京することにしました。彼女は靴を織って学費をねん出し、翟氏の生活を支えました。
10年の苦学の末、翟氏は儒学や古典、天文学などあらゆる知識を身につけ、宮廷では順調に昇進を重ねました。都では学者の間で名が知られるようになり、多くの学生が彼の門下生となりました。
同じ頃、胡常(こ・じょう)という老博士がいました。彼も古典に通じ、翟氏より位は高かったのですが、名声においては足元にも及びませんでした。翟氏に嫉妬した胡氏は、翟方進の名を聞くと、いつも激しく非難していました。
翟氏は、胡氏が彼を誹謗中傷していることを知っていましたが、気に留めませんでした。それどころか、翟氏は胡氏に会うと礼儀正しく、謙虚に接しました。胡氏が学生を集めて講義をするときは、翟氏も自身の門下生を参加させ、彼らに真剣に学ばせました。このような事がしばらく続きました。
しばらくして、胡氏は翟氏の謙虚さは本物であり、心から自分を敬っていることが分かりました。胡氏はそれまでの自分の言動を恥じ、翟氏に敬意を払うようになりました。
謙虚なふるまいは、相手の敵意をなくすことができます。古人曰く、「人と争いそうな時は、怒りを抑えて一歩引きさがるとよい。それができれば、トラブルはなくなり、道が開ける」、これは潤滑な人間関係を営む智慧です。
この物語は、『漢書』巻八十四「翟方進伝」に記されています。
『漢書』は、後漢の班固が編纂した正史であり、前漢の政治・文化・人物の姿を丹念に記録した古典です。静かに敬意を示し、相手の心を動かすそのあり方は、時代を超えて人間関係の本質を示唆しています。
(翻訳編集・郭丹丹)













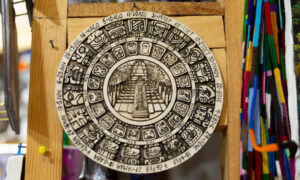










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。