アルコールへの最後の呼びかけですか? 若い世代、特にZ世代は、ソーシャルメディアとウェルネスやメンタルヘルスへの関心の高まりを原動力に、節酒革命を推進しています。
NCSolutions(広告をより効果的に)が21歳以上の1千人以上を対象に実施した消費者心理の調査では、2025年には飲酒量を減らしたいと考えるアメリカ人がほぼ半数に上ることが分かりました。この変化は、1997~2012年の間に生まれたZ世代で最も顕著であり、2025年には65%が飲酒量を減らすことを目指し、39%が完全に断酒するつもりであると回答しています。
「飲酒することや、その魅力について、あまり聞かなくなりました」と、アリヤ研究所のディレクターで、薬物使用や精神衛生上の問題を抱える若者向けのセラピストであるジャスティン・ウルフ(Justin Wolfe)氏は本紙に語りました。
これは、上の世代とは対照的です。1946~64年の間に生まれた団塊世代では、アルコール摂取量を減らす予定の人は30%しかおらず、確立された飲酒習慣を変えるつもりがないことを示しています。中には摂取量を増やしている人もいるかもしれません。
調査結果によると、65歳以上の年齢層では、アルコールの飲用が関連するとみられる健康問題が増加し懸念するほどです。最近、ノルウェーの研究で、定年退職間近の女性を含む特定のグループのなかで、特に女性がワインの飲酒量を増やす傾向にあることが明らかになりました。
最新の「薬物使用と健康に関する全国調査」によると、700万人の高齢者が、過去1か月間に暴飲を行ったと回答しています。
この世代間のギャップは、飲酒文化の将来について疑問を投げかけ、若い成人層の間で、THC(向精神薬)、キノコ(幻覚性のある「マジックマッシュルーム」)、ケタミン(アリルシクロヘキシルアミン系の解離性麻酔薬で、麻酔薬のケタラール『第一三共』)などの意識を変える代替品が増加する可能性を示唆しています。
Z世代の変化の背景にある動機
Z世代がアルコールを断つ動機は多様ですが、その中心にはソーシャルメディアが大きく関わっています。
2024年の研究調査「Frontiers in Sociology(社会学のフロンティア)」によると、Z世代は従来のソースよりも同世代のインフルエンサーから情報を探す傾向があり、デジタルメディアが価値観を形作り、広める役割をますます果たしていることが示されています。この影響力は、いくつかの方法で現れています。
世間の評価と「清純派」の美学
若い成人が世間の評価を気にするのは当然ですが、ソーシャルメディアはこうしたプレッシャーを飛躍的に増幅させます。
テキサス・クリスチャン大学の2年生でジャーナリズム専攻のソフィー・ルイズさん(Sofie Ruiz)は本紙の取材に対し、「他人からどう見られているかを気にしすぎて、だらしがないと思われるリスクを冒すことさえ嫌がる場合が多いと思います」と語りました。
この「だらしがない」と思われることへの恐怖は、「清潔な女の子」という美意識の流行によって煽られているとルイズさんは言います。ルイズさんは最近、同級生の飲酒習慣について記事を執筆しました。この美的感覚は、健康と自己管理に重点を置いていることで知られています。
「クリーンガール(清潔な女の子)」は、ピラティスの練習やグリーンスムージーの飲用、日記をつけることなど、健康的な習慣と関連付けられることが多く、お酒を大量に飲むこととは無縁です。今、人気の女の子の典型は、バランスの取れた健康的な、そして節度のあるライフスタイルを体現している人です。この理想はソーシャルメディアで盛んに宣伝され、望ましいとされるものや、憧れの対象に影響を与えています。
また、ルイズさんによると、大学のキャンパスにはYik Yakのような学校独自のソーシャルメディアアプリがあり、そこに酔った夜の画像が投稿されると、それがネット社会の黒歴史につながる可能性があるそうです。ソーシャルメディアには永続的で広範囲にわたる証拠が残るため、学生たちは永遠に好ましくない形で目撃されないようにしているのです。
評判への影響は深刻な結果を招く可能性があります。ルイズさんには、独自のInstagramアカウントを持つ大学に通う友人がいるそうです。学生はどんなものでも投稿することができるため、ある女子学生は、明らかに酔った状態で投稿したのが原因で、女子学生寮から追い出されました。
「デジタル上の足跡に対する懸念を耳にするようになって、私たちはずいぶん成長しました。人々は、そんなことで将来を台無しにしたくないのです」とルイズさんは語りました。
性別と公のイメージ
ソーシャルメディア上で特定のイメージを維持しなければならないというプレッシャーは、性別によって感じ方が異なると彼女は言います。
「社会全体として、明らかに私たちは大きく進歩したとはいえ、女の子にはより大きなプレッシャーがかかっていると思います。男の子はそれほど怖い思いをすることはないと思います。なぜなら、たとえ恥ずかしいことをして投稿されてしまっても、歴史的に見て、女の子ほど同じような影響を受けることはまずないからです」とルイズさんは語りました。
酔っ払った男の子は「ふざけている」と面白がられるだけかもしれませんが、酔っ払った女の子は「だらしない」とレッテルを貼られ、性的暴行や犯罪の被害に遭いやすくなります。
健康意識とセルフケア
ソーシャルメディアは、健康とセルフケアへの関心の高まりとも一致しています。ウルフ氏は、Z世代は自己愛と自己改善を促すメッセージに溢れていると指摘しています。自分自身を最良のバージョンにしたいという傾向があり、ソーシャルメディアがその先頭に立っています。
「不安やうつに悩んでいる場合、薬物の使用がそれをいかに悪化させるかについて、多くの証拠や喧伝があります。 そのため、人々の精神衛生は優先されていることがわかります」と彼は述べました。
ソーシャルメディアによって高まることが多いこの幸福感への注目は、若い成人たちが自分たちの生活におけるアルコールの役割を再考するきっかけとなっています。
ルイズさんは、健康を優先するためにアルコールを避ける学生がいることを認めています。
しかし、最終的には、他人からの見えざるプレッシャーに屈して禁酒する人が多いとルイズさんは考えています。
「二日酔いになりたくない、気分が悪くなりたくない、それは清純派の美意識にもつながります。ソーシャルメディアがなかったら、状況はずいぶん違っていたでしょう」と彼女は言います。
変化する偏見と社会運動の影響
ソーシャルメディアは個人のイメージだけに関わるものではありません。 アルコールに対する認識を変える、より広範な社会運動も促進しています。
ウルフ氏は、ドライ・ジャニュアリー(1月は禁酒)、ソバー・オクトーバー(10月は禁酒)などの流行が、禁酒主義者に対する偏見をなくすのに役立っていると述べています。
「定着したこれらの運動はすべて、『自分のこと、自分の体を大切にしなければならない』と訴えています。そして、人々はアルコールがその価値観にどう関係するのかを評価し、判断するようになりました。歴史的には、「お酒を飲む人」か、「断酒に取り組んでいる人」か、どちらか一方であるという見方(偏見)が常にありました。必ずしもどちらか一方である必要はありません。 その2つの領域の間には大きなグレーゾーンがあるのです」
この節度ある飲酒と自己認識のグレーゾーンは、ソーシャルメディアの影響もあり、徐々に認知され受け入れられるようになってきています。
しかし、飲酒の魅力が薄れつつある一方で、薬物乱用は増加しています。Z世代は、実は節酒の真の定義を完全に受け入れているわけではないのかもしれません。むしろ、他の意識を変えるような体験を求めているようです。
代替物質の増加
感情的な不快感を麻痺させ、そこから逃れるために飲酒が用いられることが多い一方で、ウルフ氏は、Z世代は自分の内面を探求することに熱心であり、それを助けるために他の物質を利用しているように見えると述べています。 必ずしも直接的な交換ではなく、実験と好みの変化が交差しているのです。
「振り子が反対方向に振れたようなものです」と彼は言います。
2024年秋の全米大学保健協会のエグゼクティブサマリーによると、調査対象の大学生の22.2パーセントが過去3か月間に大麻を使用したと答え、約7パーセントが幻覚剤を使用したと答えました。幻覚剤には、MDMA(一般的にエクスタシーまたはモリーとして知られている)、LSD、メスカリン、シロシビン(一般的にマジックマッシュルームとして知られている)、PCP、ケタミンが含まれます。
アメリカ国立衛生研究所が支援するこの研究では、数十年にわたって比較的安定していた幻覚剤の使用が、2020年以降、若い成人層の間で劇的に増加していることを観察しました。2021年には、過去1年間の使用経験があると報告した人の割合は過去最高の8%に達し、2016年の5%から増加しました。
一部の人々にとっては、こうした使用は、精神的な問題に対するセルフメディケーションや自己探求の手段として関連しているのかもしれません。
ウルフ氏は、「思春期の若い成人男性は、こう認めています。『自分は自分の殻に閉じこもってここに座っているのが辛い。アルコールに頼って安らぎを得ようとは思わない。自分自身で答えを見つけたい』と。彼らは、そこにある逸話的な研究を読んでおり、それは『ちょっと、これはある意味自然なことだ。自分もマイクロドーズ(幻覚剤)を試してみよう』という感じです」と言った顕著な傾向に気づきました。
彼は、人々が抑制しがちな感情的なコンテンツにアクセスする際の障壁を取り除くものとして説明されているケタミンの特定の傾向に注目しました。ウルフ氏によると、Z世代は、ケタミンを販売している情報源とつながるために、Telegramなどの暗号化メッセージングサービスを利用しています。
また、大麻の使用もより一般的になっています。アメリカ麻薬乱用・精神衛生管理庁(SAMHSA)の調査によると、2022年にマリファナの使用を開始した12歳以上の370万人のうち、120万人は12~17歳の青少年、120万人は18~25歳の若年成人でした。 若年成人のマリファナ使用は、1980年代後半以来、最も高い水準にあります。
ルイズさんは、マリファナの人気は、社会的に容認されていると認識していることが原因かもしれないと述べています。
「ハイになれば、たいていはただリラックスするだけなので、自分が恥をかいてしまうリスクは低いでしょう。一方、酔っ払っていると、自分の行動を本当に制御できませんから」と彼女は言います。
ルイズさんによると、明確な社会的グループが現れているそうです。「お酒を飲む人は以前からいますが、今では、タバコだけを吸うグループも同程度に存在しています。つまり、喫煙者か飲酒者のどちらかです」と彼女は言います。
Z世代におけるアルコール消費量の減少は明らかですが、それが他の物質の使用の直接的な増加につながるかどうかは、まだ決定的な証明はされていません。これは、節酒への真のシフト、実験、そして一部の人々にとっては別の物質への置き換えなど、さまざまな要因が組み合わさった結果であると考えられます。
ソーシャルメディアが情報の普及と薬物使用の正常化を推進している可能性もあります。Z世代の薬物使用に関する研究はまだ初期段階にあります。使用の背景にある動向や動機を完全に理解するには、さらなる研究が必要です。
飲酒文化の未来
Z世代のアルコールとの関係性の変化は、飲酒文化の将来について疑問を投げかけています。これは、ソーシャルメディアやイメージ、健康への懸念に駆られた一時的な流行なのか、それとも若者たちのアルコールや社会とのつながりに対する見方の根本的な変化なのか、まだわかりません。
マリファナや幻覚剤などの薬物の使用増加は、さらに複雑な要素を加えています。これらの代替薬物にメリットを見出すという報告もありますが、特に精神衛生や自己発見の観点では、リスクも否定できません。特に思春期の若者は、薬物の影響に特に弱く、早期の薬物使用は脳の成熟を変化させ、認知機能を損ない、物質使用障害を発症するリスクを大幅に高める可能性があります。
Z世代の薬物使用に対するソーシャルメディアの影響は複雑かつ微妙です。アルコール消費からのポジティブな変化に寄与する可能性がある一方で、違法薬物乱用のリスクを高める環境を作り出しているようです。
(翻訳編集 呉安誠)













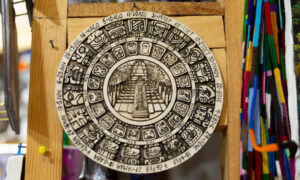










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram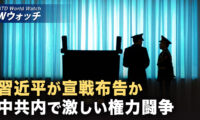




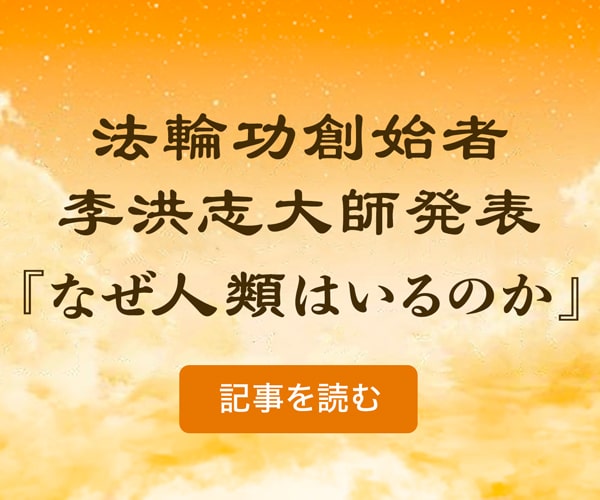
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。