「高機能性不安障害」(high-functioning anxiety)は心の病であり、つまり正式な病気ではありません。一見冷静で、きちんと生活しているように見えても、ネガティブな考えが頭から離れない、落ち着けない、緊張が解けないなどの症状が隠されています。
「ハフィントンポスト」の報道によると、アメリカ臨床心理学者のスコット・リヨンズ(Scott Lyons)氏は「高機能性不安障害」の人は、職場で仕事を上手にこなしている反面、心に不安を隠していると述べています。
その不安は複数のストレスからくると彼は説明しました。例えば、やることが多くて集中できなかったり、問題を解決する余裕がなかったり、将来をコントロールできないなどが挙げられます。
専門家は6つの特徴から「高機能性不安障害」の兆候が見えると紹介しました。
6つの特徴
●完璧主義
フロリダ州でメンタルヘルスカウンセラーを勤めるエリン・L・モラン(Erin L. Moran)氏は、完璧主義こそ「高機能性不安障害」の大きな特徴であるといいます。すべてのことに最善の結果を求めますが、できるはずがありません。完璧でなければ、自分自身を責めるか他人を非難する羽目になります。
さらに、リヨンズ氏は、「高機能性不安障害」の人と仕事をしたり、会話をしたりする際に、相手が完璧主義者であることを感じられると述べました。彼らは常に、他人の目線を気にしています。
●他人への確認や肯定に依存する
リヨンズ氏は「高機能性不安障害」の人は仕事する際に、自身の不安を和らげるために、人に確認を求めることが多いと述べました。
モラン氏は「再確認を求めることは悪いことではない、仕事にとって大事であり、必要なことである。しかし、上司や同僚に何度も再確認を頼んでしまうと、自分で判断できない、能力が足りないという印象を与えてしまう」と指摘しました。
ミシガン州の心理学者ミシェル・レノ(Michele Leno)氏も、「高機能性不安障害」の人は親しい同僚に、再確認や肯定を求めることが多いと述べました。親しい同僚は安心で信頼できる反面、それ以外の人々を避ける傾向がみられます。
●決まったことの些細な変更に過剰反応
日常業務のような決まったことは予測可能であり、不安を引き起こしませんが、わずかな変更があると、「高機能性不安障害」の人は一日中不安を感じるかもしれません。
レノ氏は「高機能性不安障害」の人は、変更を不公平だと見なし、何日も話し続けることがあると述べました。「彼らは決まったことの変更を許せないのです」
●ストレスと心配で、仕事に集中できない
「高機能性不安障害」の人は集中力が欠如し、仕事に専念できないことがよくあります。リヨンズ氏は、ヘッドフォンを着けて音楽を聴きながら仕事している人はその代表だと述べています。
「高機能性不安障害」の人は、ヘッドフォンをつけることにより、気が散るのを防ぎ、受け取る情報をコントロールできると説明しました。
●人と比較しがち
モラン氏は、「高機能性不安障害」の人が自身と他人をよく比較する根本的な原因は、不安感であるといいます。断られることが嫌、認められたいと思い、他人からの否定的なフィードバックを避けるようになります。
●いつも忙しくしている
職場で自分の価値を証明するために、「高機能性不安障害」の人は暇な時間を作らないようにしています。しかし、モラン氏は「休みがほとんどない忙しさの継続的なストレスと不安感のアンバランスが、過労を引き起こしやすい」と警告しました。
彼らは早めの出勤や残業で忙しくしています。人に頼まれたことは、ほとんど断ることがありません。
上記の兆候に少しでも心当たりがあれば、「高機能性不安障害」の可能性は否めません。深呼吸や瞑想、カウンセラーに通うなどの方法で不安をやわらげ、健康を保つようにしましょう。













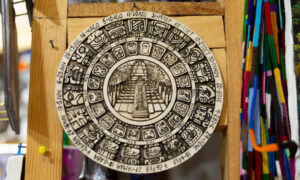







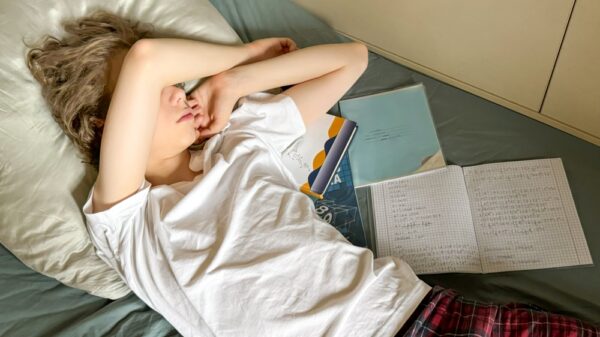

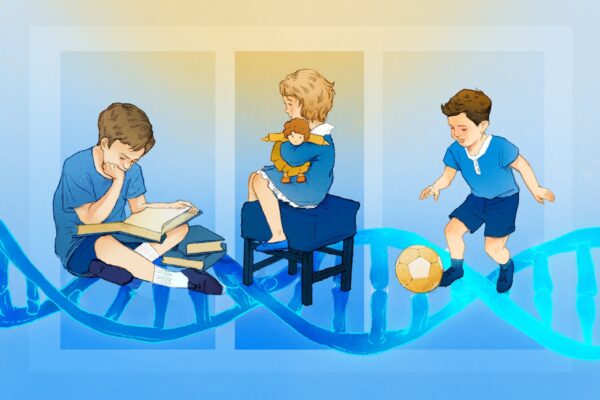
 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。