1980年のモスクワ五輪は、その前年の12月に勃発した旧ソ連のアフガン侵攻に抗議して、米国を筆頭とする西側諸国(日本を含む)が総ボイコットするという異様な状況下で開催されました。
五輪を目指して、ひたすら過酷な練習を積んできた日本の各競技の選手は、涙を流し、絶叫して五輪参加を訴えましたが、その願いは叶いませんでした。
アフガニスタンという国を、世界地図の上で、すいぶん昔(おそらく子供の頃)から眺めていたように思います。
地図で見ると、いかにも山がちな国なので、水田の広がる日本や東アジアの国とは全く異なる風景だろうと思われます。しかし紀元前から、この地には人々が生活していました。そこでは、大地に根差した寡黙な働き者が、誠実に農業を営んできたはずです。
多くは、一所懸命に麦を作っていたのでしょう。葡萄(ブドウ)の収穫期には、きっと村中が笑顔であふれていたに違いありません。
ブドウは、冷蔵庫に入れても長期保存は難しい果物です。アフガニスタンには、そんなブドウを数カ月間も保存できる伝統的な方法があるそうです。現代でも、電気事情のわるい山村では、その方法がとられています。
ガンジーナ (Gangina)と呼ばれるこの方法は、アフガニスタン北部が発祥だそうで、まずは粘土で、上下から合わせて閉じる円盤状の容器をつくり、天日で乾かします。
次に、この容器にブドウをぎっしり詰めます。空気が入らないように封をしたら、冷暗所に置くか、地中に埋めるのだそうです。うまく保存できれば、夏に収穫したブドウが冬に、秋のブドウが翌年の春に、新鮮な状態で食べられるといいます。
今は、そんなアフガニスタンの平和だった日常を想像するだけで、その風景のなかにいた名もない人々を、抱きしめたいような衝動に駆られます。
2019年12月4日、日本の中村哲医師はアフガニスタン東部のジャララバードで銃撃され、命を落としました。中村医師は、はじめ医療の方面からアフガンの復興に尽力していましたが、「根本的な復興は医療だけでは不可能だ」として、灌漑用水の整備を基盤とする農業の振興を目指します。
医師でありながら、自ら重機を操縦して水路を掘っていく中村さんの背中に、志ある日本の若者や、現地の人々が続きました。
「農業をする場があるからこそ、アフガンの人々は手にしていた銃を置き、鍬をもって耕作することができる」。中村さんは、そんな当たり前の幸せを、なんとか具現化しようとしたのです。
中村さんの「夢」は、かなり具体的な形になろうとしていました。しかし、テロリストの放った凶弾は、中村さんの命と、復興に向かうアフガンの未来を断ち切ってしまいました。中村さんたちを銃撃した犯人について、タリバンは関与を否定しています。
悲しいことに、タリバンの支配下にあって困窮したアフガンの農民は、本来の農作物ではなく、ただ金になるという理由でアヘンの原料であるケシを作っているそうです。中村医師が聞いたら、さぞや歯噛みをして悔しがるだろうと思えてなりません。
先日、テレビの画面で、悲惨きわまる光景を見ました。
アフガンからの脱出を求める群衆が空港へ殺到し、「せめて子供だけでも助けて」と、乳児とおもわれる小さな子供を、鉄条網の向こうにいる英軍の兵士に投げ渡している光景です。
受け止めた兵士も皆、泣いていたといいます。
私たち日本人の歴史も、思い返してみました。それは70数年前のこと。満州の奥地から海港のある街まで、必死の逃避行を続けてきた日本人避難民がいました。
恐るべき飢餓と病気。さらには婦女子とみれば野獣のように襲いかかるソ連兵の手を逃れてきた避難民にとって、そこはまさに生き地獄のような世界でした。
夫は徴兵され、若い妻ひとりで「なんとか祖国日本の土を踏むまでは」と頑張り続けてきたものの、ついに極限まで追い詰められ、子供を中国人に渡す(あるいは売る)ことも多くありました。それを、誰が責められるでしょうか。
アフガニスタンの人々のことを、心を痛めながら、今日も考えています。
せめて生きるために十分なパンと、瑞々しいブドウが、彼の国の人たちの口に入るように。
今はただ、それだけを祈っています。
(鳥飼聡)





















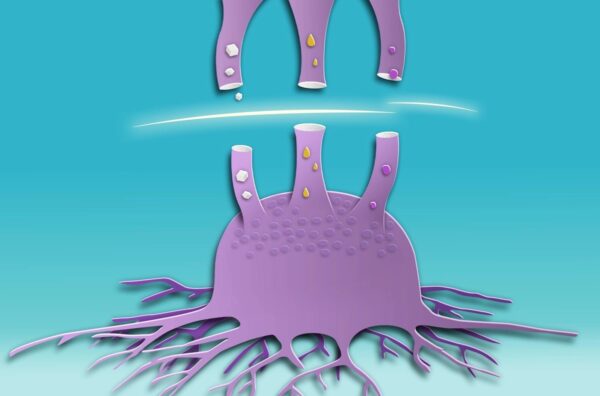

 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。