多くの人が一度は経験したことがあるでしょう。夜中ぐっすり眠っていると、突然ふくらはぎがつり、数秒から数分間、強い痛みに襲われます。カナダの公立カレッジの中医学教授であり、「康美中医クリニック」院長の劉新生(Jonathan Liu)氏が、新唐人テレビの番組『健康1+1』で、足のけいれんの原因、対処法、そして予防に役立つ食べ物について解説しました。
こむら返りの原因とは?
劉新生氏によると、ふくらはぎがけいれんする(こむら返り)原因には、次の5つがあるとされています。
1. 血行不良
ふくらはぎは心臓から遠く、重力の影響も受けやすいため、血液の流れが滞りやすい部位です。長時間立ちっぱなしの人や、動脈硬化、静脈瘤などの血管の病気がある人、また肝硬変や関節炎などの持病がある人は、血流がさらに悪くなりやすくなります。その結果、局所でのカルシウム代謝が乱れ、けいれんが起こるのです。特に夜は気温が下がり、血流が悪化しやすいため、こむら返りが起きやすくなります。
2. 運動のしすぎ
短時間に激しい運動をしたり、長時間続けたりすると、筋肉を使いすぎで疲労し、筋肉が過剰に収縮して血流が悪くなります。その結果、老廃物がたまり、カルシウムの働きにも影響が出て、筋肉が異常に収縮し、けいれんを起こすことがあります。例えば、マラソンや登山などで大量に汗をかくと、電解質が失われて筋肉内のカルシウムが不足し、こむら返りが起こりやすくなります。
3. 代謝異常・カルシウム不足
高齢者ではカルシウムの吸収が落ちてきますし、成長期の子どもや若者はカルシウムの必要量が多いのにもかかわらず、偏食などで十分に摂取できていないと、足がつりやすくなります。さらに、甲状腺機能低下症、慢性糖尿病、腎不全などの病気があると、筋肉や血管、神経に異常が起きて、けいれんを引き起こすことがあります。
4. 神経の異常
パーキンソン病や自律神経の乱れなど、神経系の不調によって筋肉の動きがコントロールできなくなり、ふくらはぎがつることがあります。このタイプのこむら返りは比較的重症です。
5. 薬の副作用
降圧剤や利尿剤などの薬を飲むことで、尿と一緒に水分だけでなく必要な成分まで排出されてしまい、脱水や電解質のバランスが崩れて、けいれんが起こることがあります。
悪い姿勢とこむら返りの関係
劉新生氏によると、足のけいれん(こむら返り)は体の姿勢とも関係する場合があります。たとえば、先天的に足の構造に異常があるケース(扁平足、膝が反り返る膝過伸展、足首の不安定さなど)や、長時間の座りっぱなし、悪い姿勢を続けていることが原因で、ふくらはぎの筋肉(腓腹筋)が緊張しやすくなります。つまり、筋肉の張りが強くなりすぎている状態です。ふくらはぎの後ろにある腓腹筋は、膝と足首をつなぐ筋肉で、この筋肉が収縮すると足先を下に向ける動きが起こります。
夜間に腓腹筋の緊張が高いままになっていると、ふくらはぎ周辺の血流が悪くなり、けいれんを引き起こしやすくなります。これが主な内的要因です。さらに、布団が重すぎて足先が常に下向きになっていると、腓腹筋がずっと収縮した状態になり、それもけいれんのリスクを高めます。これが外的な要因の一つです。
こむら返りを自分で和らげる方法
けいれんが起きたとき、多くの人がまず反射的に、つった部分を揉んでしまいがちです。しかし、劉新生氏はこれは最善の方法ではないと指摘します。痙攣している部分を強く刺激すると、かえって症状が悪化するおそれがあるからです。
もっとも簡単で効果的なのは、「足のつま先を上に引き上げる」ことです。これによりふくらはぎの腓腹筋がしっかりと伸び、けいれんを抑えて痛みをやわらげることができます。
それでもけいれんが治まらない場合は、手でつま先をつかみ、ゆっくりと膝の方向に引っ張ってみてください。このとき、動きはゆっくりとやさしく行い、急に強く引っ張らないよう注意します。そのあと、脚をゆっくりと伸ばしていきます。これによって腓腹筋がゆるみ、こむら返りをすばやく解消することができます。
中医学によるこむら返りの治療法
劉新生氏によると、後漢時代の名医・張仲景が著した『傷寒論』には、こむら返りの治療に用いられる有名な漢方薬「芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)」が紹介されています。
【材料】白芍(びゃくしゃく)30g、甘草(かんぞう)10g
【作り方】薬材を600mlの水に入れ、約200mlになるまで煮詰めます。煎じた薬をこして滓を除き、2回に分けて温かいうちに服用します。
【効果】筋肉のけいれんを和らげ、血行を促進し、下肢の静脈血栓の軽減や予防にも効果があるとされています。
中医学では、経絡は体内のエネルギー(気)の通り道であり、臓器と体の各部位をつないでいると考えられています。この経絡上には「経穴(ツボ)」と呼ばれるポイントがあり、鍼灸やマッサージでこれらのツボを刺激することで、さまざまな症状を改善することができます。
劉氏は、ふくらはぎの腓腹筋は「膀胱経」という経絡に沿っているため、その経絡上にあるツボを刺激することで、筋肉のけいれんを緩和できると説明しています。中でも「承山(しょうざん)」というツボは、こむら返りに特に効果的とされており、ここに鍼を打って「ズーンと響くような刺激」を感じると、症状が和らぎます。
症状が強い場合は、「委中(いちゅう)」や「崑崙(こんろん)」など、同じく膀胱経上にあるツボを併用することで、より素早く痛みを軽減できます。
また、鍼だけでなく、ツボのマッサージも効果的です。こむら返りが起きたときには、承山を指圧することで応急的に症状を和らげることができます。さらに「陽陵泉(ようりょうせん)」というツボも合わせて刺激すると、筋肉や関節全体のバランスを整えるのに役立ちます。高齢者には「太渓(たいけい)」というツボのマッサージもおすすめです。腎の働きを助け、筋肉や骨の衰えを予防・改善する効果が期待されます。
栄養を補ってこむら返りを予防しよう
劉新生氏によると、体内のカルシウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウムなどの電解質のバランスが崩れると、こむら返りが起きやすくなります。以下のような食品で、これらの栄養素を補うことが勧められています。
1. バナナ
バナナは、こむら返りの予防にもっとも適した果物のひとつです。カリウム、マグネシウム、カルシウムといった、筋肉のけいれんを防ぐ栄養素が豊富に含まれています。手軽に食べられる点も魅力です。
2. 質のよい炭水化物を含む食品
サツマイモ、ジャガイモ、カボチャなどは、カルシウム、カリウム、マグネシウムが豊富に含まれています。ジャガイモやカボチャは水分も多く、脱水によるこむら返りの予防にもつながります。
3. アボカド
アボカドはカリウムの宝庫です。カリウムは筋肉の働きを助け、心臓の健康にも役立ちます。研究によると、アボカドを週に1個以上食べる人は、食べない人に比べて心血管疾患のリスクが16%、冠動脈疾患のリスクが21%低下するという結果もあります。脂っこい食品の代わりにアボカドを使うのも良い方法です。
4. 豆類
赤インゲン豆や黒豆などは、マグネシウムと食物繊維が豊富です。血糖値のコントロールを助けるほか、悪玉コレステロール(LDL)を下げる効果もあり、心臓の健康維持に役立ちます。
5. ウリ科の果物
メロン、マクワウリ、パパイヤなどには、マグネシウムやカルシウム、水分が多く含まれており、少量のナトリウムも含まれます。運動で汗をかいたあとに食べることで、電解質を補い、筋肉の緊張をやわらげるのに役立ちます。
6. 牛乳
牛乳はカルシウム、カリウム、ナトリウムがバランスよく含まれているうえ、たんぱく質も豊富なので、運動後の筋肉回復にも効果的です。
7. 濃い緑色の野菜
ケール、ホウレンソウ、ブロッコリーなどの濃い緑の葉野菜は、カルシウムやマグネシウムが豊富で、骨や筋肉の健康に役立ちます。
8. オレンジジュース
オレンジジュースには、ビタミンCだけでなく、カリウム、カルシウム、マグネシウムも多く含まれており、電解質のバランスを保ち、筋肉のけいれんを防ぐのに効果があります。
9. ナッツや種子類
ピーナッツ、ヒマワリの種、クルミなどは、マグネシウムとカルシウムが豊富です。さらに、不飽和脂肪酸を含んでおり、心臓の健康を守るとともに、ビタミンDなどの脂溶性ビタミンの吸収を助けることで、カルシウムの吸収も促進し、骨の健康に良いとされています。
10. トマト・トマトジュース
トマトは水分とカリウムが豊富で、体内のカリウムとナトリウムのバランスを整え、生理機能を調節するのに役立ちます。
こむら返りは病気のサインかもしれない
ふくらはぎがつる(こむら返り)症状は、一時的なものと考えられがちですが、発作が頻繁になったり、症状が重くなったりする場合は注意が必要です。
劉新生氏は、こむら返りが特定の病気の一症状である場合もあるため、繰り返しけいれんが起きる人は、病院での検査を受けることを勧めています。以下は、こむら返りに関係する可能性のある病気です。
・ 糖尿病
糖尿病は筋肉や骨の機能に影響を及ぼし、筋肉のけいれんはよく見られる症状のひとつです。原因がわからない突然の強いこむら返りが起きたときは、血糖値の検査を受けることが重要です。
・ 関節炎
特に多いのが膝の関節炎で、ふくらはぎの筋肉が一般の人より疲れやすくなり、けいれんが起こりやすくなります。カルシウムを摂ったり牛乳を飲んだりしても改善されない場合、関節炎の可能性があります。
・ 肝硬変
特に進行した肝硬変では、体内のカルシウム、カリウム、マグネシウムなどの電解質のバランスが崩れやすくなり、筋肉がつりやすくなります。
・ 心血管疾患
心不全などの心臓の病気や、深部静脈血栓などの血管の病気も、筋肉のカルシウム代謝に影響を与え、けいれんを引き起こす原因となります。
・ 神経障害
自律神経の乱れや末梢神経の障害によって、足のけいれんが起きることがあります。この場合、痛みやしびれを伴うことが多いです。
これまでに紹介された漢方薬や食品の中には、聞き慣れないものもあるかもしれませんが、多くは健康食品店やアジア食材の店などで手に入ります。ただし、人によって体質や体の状態が異なるため、使用する前に専門の医師に相談することをおすすめします。
(翻訳 華山律)













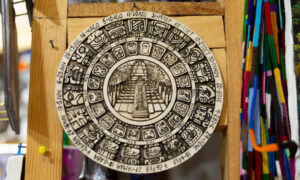










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。